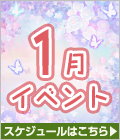「まさに戦争だよ」深刻なクマ被害の現状と課題
- カテゴリ:ニュース
- 2025/11/12 23:52:15
「まさに戦争だよ」秋田県のクマ被害が深刻化…小泉防衛大臣、自衛隊派遣で装備には“木銃”を採用 (ABEMA TIMES)
https://news.yahoo.co.jp/articles/b83fc24b24432810d4ef8d49fcd65fc236e0cd8b
クマ被害と自衛隊派遣から考える日本の害獣対策の現状と課題
1. 秋田県クマ被害の深刻化と自衛隊の役割
秋田県ではクマによる人身被害が深刻化し、元知事が「まさに戦争」と表現する事態に発展しました。これを受け、防衛省は陸上自衛隊を派遣しましたが、現行法ではライフルなどの武器をクマに使用できないため、任務はわなの運搬や解体など後方支援に限定されました。
自衛隊員が装備するのは、殺傷能力のない「木銃」(木製の銃型)とクマスプレーです。これは、手負いにしたクマの凶暴化リスクを避けるためと、隊員の安全を正当防衛の範囲内で確保するための措置です。
2. 銃器使用の法的制約と「駆除」と「防衛」の違い
自衛隊が任務としてクマを駆除できないのは、銃器による動物の殺傷が警察官や猟友会の権限であり、自衛隊は「治安出動」などの例外を除き、警察権を行使できないという現行の法律(銃刀法、鳥獣保護管理法など)による制約があるためです。
・正当防衛: 演習中などでクマに襲われ、生命の危機に瀕した場合は、正当防衛として銃器の使用が認められる可能性はありますが、これは「自己防衛」であり、自治体支援としての「駆除任務」とは異なります。
3. 過去の特異な事例と現代の課題
かつて(1950年代後半〜1960年代)北海道では、漁業被害対策として自衛隊がトドを「射撃訓練」の名目で駆除した特異な事例がありました。しかし、厳格な法規制が敷かれている現代では同様の実弾を用いた駆除は不可能です。
4. 猟友会の負担軽減と公務員ハンターの提案
深刻化する鳥獣被害への対策の担い手である猟友会の高齢化と人手不足が課題となっています。
・銃器管理の負担: 銃の所持や維持にかかる経済的・手続き的な負担も懸念されています。銃を市町村や県が管理する案は負担軽減に有効ですが、現行の銃刀法では銃の所持主体は個人(または警察・自衛隊)に限定されており、自治体による「貸与制度」を行うには法改正が必要です。
・公務員ハンターの有効性: 対策の継続性確保と専門性向上のため、自治体が公務員ハンターを雇用する動きがあり、その中でも警察や自衛隊のOB(退職者)を登用することは極めて有効な解決策となります。OBは銃器の安全管理や危機対応の専門性が高く、自治体と専門組織との連携強化に貢献できると期待されます。
現行の法制度では、銃を自治体や警察が管理し、個人に貸与する運用は非常に困難なため、公務員ハンターを導入している一部の自治体でも、銃器の所有・管理については職員個人に任せ、その費用の一部を自治体が補助するという運用が一般的です。
5. 警察官によるクマ駆除に関する国家公安委員会規則の改正
警察庁は、クマによる被害への対応強化と、現在の対策が抱える課題の解決のため、警察官がライフル銃を用いてクマを駆除できるよう、国家公安委員会規則を改正しました。この改正は、11月13日に施行されます。
これまでクマ対策は猟友会に依存してきましたが、猟友会の高齢化と担い手不足の深刻化により、緊急時の即応性や制度の持続性に限界が生じていました。今回の規則改正により、警察官が駆除の権限を持つことで、以下の体制が整備されます。
・即応性の向上: 猟友会がすぐに現場へ急行できない場合にも、行政(警察)が迅速に対応可能になります。
・危険な状況への対応: 危険度の高い市街地での駆除要請に対し、警察が責任を持って対応できるようになります。
この措置は、行政によるクマ対策の体制を強化するものであり、「公務員ハンター制度」と並び、猟友会への過度な依存を解消し、持続可能な行政対応を実現するための重要な一歩として期待されます。
関連記事
警察官によるライフル銃での“クマ駆除”可能に 国家公安委員会規則を改正 来週13日に施行 (TBSテレビ)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2272924