十三夜
- カテゴリ:美容/健康
- 2025/11/02 17:08:45
ニコットおみくじ(2025-11-02の運勢)

こんにちは!九州から関東は大体晴れるが所々で雨。
北陸、東北、北海道は日本海側を中心に雨や雷雨。
沖縄は晴れ。
気温は全国的に平年並みか高い。
【十三夜】 じゅうさんや
☆十三夜は、旧暦9月13日の夜に月を鑑賞する日本独自の月見行事です。
十五夜の約1カ月後に行われ「後の月」とも呼ばれます。
<概要>
〇十三夜
十三夜は、旧暦の毎月13日の夜のことを指し、
特に旧暦の9月13日に巡ってくる月のことをいいます。
十五夜のことを「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」といいますが、
十三夜は十五夜の約1カ月後に巡ってきます。
@別名
十三夜の別名を・・・
・後の名月(のちのめいげつ)
・後の月(のちのちき)
このようにいいます。
他にも、栗や大豆(枝豆)をお供えすることから・・・
・栗名月(くりめいげつ)
・豆名月(まめめいげつ)
このようにも呼ばれています。
@十三夜に曇り無し
十五夜の頃にはまだ夏の暑さが残っていまして、
雨が多いので、スッキリしない夜空が多いのですが、
十三夜の頃になりますと、晴れの日が多く、
涼しくなって、空気も澄んでいるので月が美しく見えます。
その為・・・
「十三夜に曇り無し」
このような言葉があります。
★中秋の名月と十三夜の日付と天気
□中秋の名月
西暦 中秋の名月 東京の天気 大阪の天気
2008年 9月14日 曇りのち雨 曇りのち晴れ
2009年 10月 3日 晴れのち曇り 曇りのち晴れ
2010年 9月22日 曇りのち晴れ 曇りのち雨
2011年 9月12日 晴れ 晴れのち曇り
2012年 9月30日 雨のち晴れ 曇りのち雨
2013年 9月19日 晴れ 晴れ
2014年 ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー
2015年 9月27日 曇りのち晴れ 晴れのち曇り
2016年 9月15日 曇りのち晴れ 曇り
2017年 10月 4日 曇りのち晴れ 晴れのち曇り
■十三夜
西暦 十三夜 東京の天気 大阪の天気
2008年 10月11日 晴れ 晴れ
2009年 10月30日 晴れ 晴れのち曇り
2010年 10月20日 曇りのち雨 曇りのち雨
2011年 10月 9日 曇りのち雨 晴れのち曇り
2012年 10月27日 曇りのち雨 曇りのち雨
2013年 10月17日 曇り 曇り
2014年 11月 5日 曇り 曇りのち雨
2015年 10月25日 晴れ 晴れ
2016年 10月13日 曇り 曇り
2017年 11月 1日 晴れ 晴れ
過去10年の東京都大阪の天気を見ますと、
十五夜で張れた(晴れ間の出た)のは東京は10年で8回、
大阪は10年で7回となり、かなりの確率で月が見れたことが分かります。
一方、十三夜に晴れた(晴れ間の出た日)のは、
東京は10年で4回、大阪は10年で5回と、
十五夜に比べますと月を見れていないことが分かります。
そもそもこの言葉は、1000年にわたるお月見文化の中で、
培(つちか)われてきた経験則から伝えられて言葉で、
過去10年の比較ではほとんど参考にはなりませんが、
少なくとも、ここ最近の傾向では少しずれているようです。
@2025年の十三夜
旧暦の9月13日は、新暦では10月の中旬から下旬の頃に巡ってきます。
2025年の十三夜は、11月2日(日)です。
旧暦9月13日の日付を新暦に直しますと、
毎年ずれが生じる為、十三夜の日付は毎年異なります。
@十三夜の由来
十五夜や平安時代(794~1185年)頃に、
中国から伝わり広まった風習ですが、十三夜は日本固有の風習です。
旧暦9月13日なのかは、諸説あります。
☆宇多天皇が由来という説
藤原宗忠(ふじわらのむねあだ)さんの
「中右記(ちゅうゆうき)」という日記の中に、
第59代天皇の宇多天皇(在位:887~897年)が、
旧暦9月13日の月を愛で「今夜の名月は並ぶものが無い程、優れている」。
このように称賛しまして、この日を「名月の夜」と定めたと、
書かれていまして、これが由来という説があります。
*藤原宗忠さん・・・1062~1141年、平安後期の公家
★醍醐天皇が由来という説
延喜19年(919年)に、
第60代天皇の醍醐天皇(在位:897~930年)が、
十五夜の宴に加えて、旧暦9月13日にも観月の宴を行ったのが、
十三夜の月見の始まりという説があります。
醍醐天皇の父親である、
宇多天皇が旧暦9月13日の月を愛でていたことから、
醍醐天皇の時代には既に十三夜を愛でる風習が、
あったのではないかと考えられています。
☆収穫祭が由来という説
旧暦9月13日は、稲の収穫を迎える地域が多いことから、
十三夜は秋の収穫祭の一つだったのではないかという説があります。
@十三夜の食べ物
十五夜と同じように、
十三夜でも芒(すすき)や月見団子をお供えします。
それ以外にも・・・
・クリ ・ダイズ
・ジャガイモ ・ダイコン
・レンコン
★秋の七草
・オバナ ・ナデシコ
・フジバカマ ・キキョウ
・ハギ ・オミナエシ
・クズ
お供えをして感謝をした後は、美味しくいただきます。
これら等、秋に収穫された野菜や秋の七草をお供えします。
これらをお供えするのは、収穫や豊作に感謝する意味があります。
問題 十三夜は十五夜に次いで美しい月といわれまして、
一般的に十五夜にお月見をしたら、
十三夜にも必ずお月見をするものとされていました。
その為、どちらか一方の月しかお月見をしないことを、
何と呼ぶのかについてですが、〇〇に入る言葉を教えてください。
1、独眼
2、片見
3、片目
ヒント・・・〇〇〇月
十五夜と十三夜のどちらか一方しか月見をしないことを指しまして、
縁起が悪いとされています。
@江戸時代の風習
江戸時代の武家社会や貴族の間では、
十五夜から十三夜まで続けて月見を行うことが、
教養と誠実さの証とされていました。
☆途中で止めてしまう「〇〇月」は忌(い)み嫌われた
・物事を最後まで続けない不誠実さ
・季節の移ろいを十分に味合わない粗雑さ
・伝統文化への敬意の欠如
*絶対駄目という意味ではなく、
あくまで当時の価値観に基づく云い伝えです
「〇〇月」は、不幸が起こる等ではありません
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。





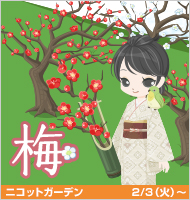







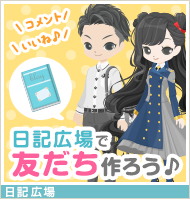












こんにちは!祝日「文化の日」のお忙しいところ、
こうしてコメントとお答えをどうもありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
はい、おみくじは「大吉」でした。
どうもありがとうございます。
そうですか、なかなか夜に夜空を観る機会が少ない方も多いですね。
問題の答えですが、2番の片見が正解になります。
どうもおめでとうございます(祝)
昨日のお月様は、美しかったですよ。
昔の方は、このお月様を眺めて、色々なことを考えたりなされたのでしょうね。
十三夜、私は夜空を観る機会が殆どないので、
十五夜含めても、片手でも数えられるかどうかです。
答え 2