統計の日
- カテゴリ:アート/デザイン
- 2025/10/18 01:06:48
こんばんは!18日(土)は、北日本や北陸、
それに西日本では午後を中心に雨が降り、
雷を伴って激しく降る所があるでしょう。
東日本太平洋側は雲が広がりやすく、夜には雨の降る所がある見込みです。
南西諸島は晴れたり曇ったりとなり、所によりにわか雨や雷雨がありそうです。
【ハロウィンコーデ/コーデ付き日記投稿イベント】
A、ジャックランタン バレッタです。
【統計の日】 とうけいのひ Statistics Day
☆「統計の日」(10月18日)は、
統計の重要性に対する国民の皆様の関心と理解を深め、
統計調査に対する、より一層の協力の推進することを目的に、
昭和48年に定められました。
<概要>
〇統計の日
@統計の日の成り立ち
★統計の歴史と始まり
統計の日は、
1973年(昭和48年)7月3日の閣議了解によって制定されました。
しかし、その歴史はもっと古く、
1870年(明治3年)に遡(さかのぼ)ります。
この年に「府県物産票」に関する太政官布告が公布され、
それが日本の生産統計の起源となりました。
この「府県物産票」は、日本の近代化の歩みとも密接に関連しています。
国家としての体系を整え、国際的な競争に備える為には、
正確なデータに基づく政策が求められたのです。
□府県物産票と日本の近代化(鳥取県編)
その由来は、明治3年9月24日(現在の暦で10月18日)、
当時の政府が地方に対して行った布告です。
内容は各管内の物産調査を指示するもので、
成果として農林水産業や鉱工業を網羅した製品別産出高が、
府県単位で公表されました。
現代の目で見ると不充分な精度ではあるものの、
これが日本の近代的産業統計の先駆けといわれています。
下記が当時の公表資料「府県物産票」から、
明治7年の鳥取県で産出高(金額ベースが)大きかったものです。
◆明治7年の鳥取県の主な製品産出額
米 ーーーーーーーーーーーーーーー
146、0
醸造物類 ーー19、9
縫織物類 ーー16、7
錦類 ーー16、0
麦 ーー14、0
金・銀・銅・鉄類ーー11、7
0 50 100 150
(万円/年)
(注)年間産出額が10万円を超える6品目のみを表示。
分類区分は資料のまま。
資料:内務省勧業寮編「明治七年府県物産表」
(海路書院刊行の復刻版より)。
グラフの通り、米の存在感は圧倒的です。
麦の産出高も大きく、主穀生産が県経済の中心だったことが分かります。
清酒をはじめとする醸造業も主要産業でした。
又、錦類や縫織物類の大きさは綿作や錦織物業が盛んだったこと、
金・銀・銅・鉄類の大きさは、タタラ製鉄の産地だったことを示しています。
明治時代の鳥取県では、かつて主要産業だった錦作・錦織物業は、
次第に養蚕・製糸業(生糸製造)に取って代わられ、
タタラ製鉄も衰退へと向かったことが知られています。
「府県物産表」は、そうした変化以前の県の姿を記録するとともに、
歴史資料としての統計の重要性を私達に伝えています。
◇「タタラ製鉄」の衰退と復活
▲「出雲鉄」の隆盛と衰退ーー伝統的製鉄の燗熟期
中国地方の鉄は幕末(1853~1668)年から明治初頭にかけて、
国内の鉄生産量の8割~9割という圧倒的なシェアを獲得していました。
しかし、明治の開国によって洋鉄が大量に楡雄されるようになると、
和鉄は急速にその地位を失っていきます。
▽和鉄
・日清戦争(1894~1895)年
・日露戦争(1904~1905)年
・第一次世界大戦(1914~1918)年
これらの特需により、一時的な回復を見せますが、
やがて安価な洋鉄に駆逐される形で、
日本の伝統的製鉄法は途絶することとなりました。
その後、タタラ製鉄は第二次世界大戦(1939~1945)年の、
軍刀需要により一時的に復活しますが、敗戦により、再び廃止されます。
△「タタラ」の復活ーー日刀保(にっとうほ)タタラ
「タタラ」の代名詞ともいえる日本刀は、
日本が世界に誇ることの出来る鋼の工芸品です。
その作刀には、日本古来の製鉄法であるタタラによって生産される和鉄、
中でも良質な鋼である貴重な玉鋼(たまはがね)が不可欠です。
▼玉鋼
タタラで得られた鉧「けら(粗鋼塊)を破砕し、
特に不純物の少ない良質の部分だけを取り出したものです。
玉鋼は純度の高い炭素鋼で元々刃物に適していますが、
これに折り返し鍛錬を施すことで、
含まれる不純物が排出されるとともに、
適度に分散介在して、刃物とした際の粘り強さを与える、
研ぎ性を高める等、刃物鋼としての性質を向上させて、
又、微妙な肌模様を作り出すことで、
刀の美しさにも寄与していると考えられています。
このように日本刀に不可欠な玉鋼ですが、
昭和8年(1933年)から昭和20年(1945年)にかけて、
奥出雲町で操業された「靖国鈩(やすくにたたら)」を最後に、
以後、ほとんど生産されていませんでした。
問題 この日本刀が復活するのですが、
次の文章の〇〇に入る言葉を教えてください。
第二次世界大戦後、
占領軍の没収によって絶滅の危機に瀕していた日本刀を混乱から救い、
これを後世に伝えることを目的として、
昭和23年(1948年)、当時の文部大臣の認可によりまして、
公益財団法人・日本〇〇刀剣保存協会さんが設立されました。
以来、公益財団法人・日本〇〇刀剣保存協会さんは、
〇〇工芸品として価値ある刀剣類の保存と公開、
重要無形文化財としての日本刀の鍛錬や研磨、
刀装制作技術等の保存と向上に努めてきました。
この取り組みの一環として、公益財団法人・日本〇〇刀剣保存協会さんは、
昭和52年(1977年)、旧「靖国鈩」を「日刀保タタラ」として、
復活させました。
1、芸術
2、宝飾
3、美術
ヒント・・・〇日本刀の〇〇工芸品としての特徴
@折り返し鍛錬による〇と強靭さ
鋼を何度も折り返し叩くことで、地肌を生み出します。
@刀文(はもん)の芸術性
直刃、職人の〇意識が反映されています。
@拵(こしらえ)の装飾性
蒔絵の鞘や金具等装飾が施された拵が多く造られました。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。





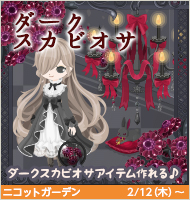

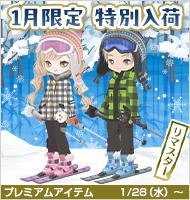












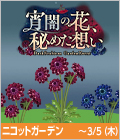





こんばんは!日付が変わりまして土曜日ですね。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、米の存在感は昔からですものね。
問題の答えですが、3番の美術です。
素晴らしいですね!どうもおめでとうございます(祝)
そうですね、歴史のある日本刀が廃れないで良かったですね。
米の存在感は圧倒的ですね。
答え 3
日本刀が廃れないで良かったです。