法の日
- カテゴリ:人生
- 2025/10/01 00:43:25
こんばんは!1日(月)は、北日本から東日本では曇りや雨となり、
雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。
落雷や竜巻等の激しい突風、降雹、急な強い雨に注意してください。
西日本や南西諸島は概ね晴れますが、にわか雨や雷雨の所もある見込みです。
【好きなYouTuveチャンネルは?】
A、YouTuveはあまり視ないのですが、歴史番組があると面白そうですね。
【法の日】 Day of Law
Law Day
☆法の日は10月1日に設けられた記念日で、
法の役割や重要性を考えるきっかけとなります。
<概要>
〇法の日
@「法の日」の起源に迫る
1928年(昭和3年)に陪審法が施行されたこの日は、
日本の日本史において重要な節目とされています。
翌1929年(昭和4年)からは、
この日が「司法記念日」として制定されました。
法の重要性は四方に対する理解を深める為の日として、
司法制度の根幹をなす陪審法の施行日を記念しています。
しかし、なぜこの日が選ばれたのか、
その背景にはどのような歴史的経緯があるのでしょうか。
実はこの日は日本の近代化を象徴する出来事として、
法の村長を国民に広く呼びかける為の象徴的な意味合いを持っています。
このように、記念日にはそれぞれの背景があり、
その背景を知ることで、より深い理解が得られるものです。
「法の日」は、単に過去の出来事を振り返るだけではなく、
現代社会における法の役割や意義を再確認する機会として、
私達にとって、非常に価値のある日です。
★陪審法
1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで、
日本では国民が裁判に参加する陪審制を取り入れていました。
戦前における陪審員制はイギリスやアメリカのそれと同じく、
事実認定を陪審員のみが行っていましたが、
現在の死版員制度では裁判員と裁判官がともに決定する点が、
大きく異なります。
明治時代の前半の段階で、
既に憲法や治罪法(刑事訴訟法の全身)の制定をめぐり、
民間で陪審制の採用が主張されるだけではなく、
政府のレベルでもその導入は検討されていました。
◇明治時代の前半の治罪法
日本の刑事手続を近代化する為に、重要な役割を果たしました。
治罪法はフランスの治罪法を参考に編纂された独立法典であって、
公訴と私訴の区別、刑事裁判所の構成、起訴の原則、
予審制度等が定められました。
これによりまして、日本の刑事裁判手続きが近代化され、
司法制度の整備が進められました。
治罪法は明治時代初期に制定された日本初の刑事訴訟法典であり、
江戸時代の慣習的な裁判手続きから脱却し、
フランス法を参考に近代的な刑事裁判制度を確立しました。
この法律は、その後の日本の法体系に大きな影響を与えました。
しかし、結局のところ、陪審制は制定された治罪法や大日本帝国憲法、
治罪法は書き込まれませんでした。
こうして実現の可能性が無くなったと思われていた、
陪審制を強く推進したのが、日本初の本格的政党内閣の、
首相となった原敬(はらたかし)さんでした。
原敬さんは人権擁護や司法の民主化を掲げまして、
又、司法権の独立を盾に独自の政治勢力となった、
司法官僚の抑制を狙っていました。
原敬さんが暗殺された後も、
陪審法案は、続く高橋是清(たかはしこれきよ)内閣、
加藤友三郎(かとうともさぶろう)内閣によって引き継がれまして、
1923年(大正12年)に成立しました。
陪審法案は1928年(昭和3年)に施行されまして、
日本における陪審制が始まります。
その対象は死刑及び無期懲役・禁錮がかかる事件(法廷陪審)でありまして、
そして3年以上の懲役・禁錮がかかる地方裁判所の直轄に属する事件で、
かつ被告が希望する場合(請求陪審)でした。
皇室や軍事機密に関わる事件は対象外でした。
又、陪審員の出した答申を退けて、
別の陪審にかけることが出来る(陪審の更新)等、
判事の権限は強いものでした。
陪審員は国民全てに資格があった訳ではなく、
直接国税を3円以上収め、読み書きの出来る、
30歳以上の男子に限定されていました。
同じ年から施行された普通選挙法に納税の条件が無く、
25歳以上の男子、全てに選挙権を与えていたのとは対照的でした。
スタートした陪審制度ですが、
自動的に対象となるはずの法廷陪審でも辞退が許されていまして、
又、陪審員の対象になると控訴が出来なくなる等の理由から、
法廷陪審は多く辞退され、請求陪審の請求は極めて少なかった為、
陪審裁判の数は事前予想を遥かに下回りました。
*陪審制の対象になると控訴が出来なくなる:
当時の最高裁判所である大審院への上告は出来る
ただし、陪審裁判の無罪率は高かったといわれています。
さらに、無罪のみならず、公訴事実よりも軽い罪が認定された場合も多く、
これらを足し合わせますと、3~4割程度になったと推定されています。
*無罪のみならず、公訴事実よりも軽い罪が認定された場合:
殺人が傷害致死に、殺人未遂が障害になる等のケース
勿論、陪審裁判の数が少ないにも関わらず、あえて陪審を辞退しない、
もしくは陪審を請求した被告の無罪や罪の軽減の例が、
多くなるのは当然ともいえます。
しかし、こうした傾向は判事や検事達を大いに困惑、警戒させていまして、
少なくとも陪審が形骸化していなかったことの、
証拠になる可能性はあります。
戦争の時代を迎えますと、陪審裁判数はさらに減りまして、
戦争に関わる業務の激増で疲弊する市町村の役所からは、
陪審員資格者や候補者名簿を作成する事務を、
取りやめにする為に陪審法を廃止してほしいという、
要望が多く寄せられるようになりました。
しかし、戦争が終わっても陪審制が復活することはありませんでした。
*復活することはありません:
アメリカ統治下の沖縄では、
アメリカ民政府裁判所において、1963年から刑事陪審制が、
1964年から民事陪審制が陪審員の国籍を問わずに実施されましたが、
本土復帰とともに廃止されました
問題 1960年(昭和35年)裁判所や検察庁、弁護士会の進言によりまして、
法務省がこの日を「法の日に」制定しましたが、
「法の日」の目的について、次の文章の〇〇に入る言葉を教えてください。
〇主な目的
法の〇〇や重要性を国民に考えてもらうことが主な目的です。
@法
社会秩序を保ち、基本的人権を擁護する為に不可欠です。
この日は、
法を通じてより良い社会を目指す精神を高める為に設けられています。
1、役割
2、義務
3、意味
ヒント・・・〇法の〇〇
社会の秩序を保ち、
人々が安心して暮らせる環境を整える為に非常に重要です。
法は単なる「縛るもの」ではなく、
私達の自由や安全を守る為の基盤として存在しています。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。




















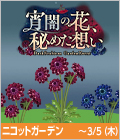





こんにちは!曇りの木曜日をお疲れ様です。
そうですね、陪審員が安定するまでは大変だったようですね。
問題の答えですが、1番の役割が正解になります。
スズラン☆さん、どうもおめでとうございます(祝)
このように、そもそも法律は民「縛る」ものではなくて、民を「助ける」ほうですね。
勉強になりました。
答え 1