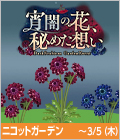立憲野田氏 自民に総裁選ステマで調査を求める
- カテゴリ:ニュース
- 2025/09/30 00:28:51
立憲・野田代表 総裁選“ステマ”で自民に調査を求める考え (TBS)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2195277
立憲民主党の野田代表は、自民党総裁選で小泉陣営の広報責任者だった牧島元デジタル大臣の事務所が、動画サイトに小泉氏に好意的な書き込みを関係者に依頼していた問題について、過去の国政選挙でも野党に対して行われていた可能性があると指摘し、自民党全体での調査を求めました。
野田代表が指摘されたように、仮に本件が総裁選のみならず、過去の国政選挙においても同様の手法により野党に不利な世論操作が行われていたとすれば、民主主義の根幹を揺るがす重大な問題であると言わざるを得ません。インターネット上での世論操作は可視性が低く、かつ拡散力が極めて高いため、その実態を把握し、検証することは極めて重要です。
また、選挙以外の場面においても、政治的ステルスマーケティング(以下、ステマ)による世論操作が行われているのではないかと疑念を抱く方が出てくる可能性は十分に考えられます。
特定の商品やサービスに関するステマは景品表示法により禁止されておりますが、総裁選は同法が想定する「商品やサービスの取引」には該当しないため、直接の適用対象外となり、法的には違法とはされません。しかしながら、「法律で禁止されていないから問題ない」とするのは、倫理的観点から看過できるものではありません。
政治的ステマとプロパガンダは、手法や規模においては異なるものの、「世論を誘導する」という目的においては本質的に共通しております。政治的ステマは以下のような構造的特徴により、より悪質性を帯びる可能性があります。
◯政治的ステマの不可視性がもたらす悪質性
・発信源の偽装:プロパガンダは政府や政党の名義で公然と発信されることが多い一方、政治的ステマは「一般市民の声」や「自然な支持」に見せかけて発信されるため、受け手が警戒しにくいという特性があります。
・自然な拡散性:SNSや動画のコメント欄などにおいて、好意的な書き込みや批判的な書き込みが“自発的”に見えることで、情報の信頼性が高まる傾向があります。しかし、実際には組織的に仕込まれている可能性も否定できません。
・検証の困難性:誰が発信したのか、どこから指示が出されたのかを追跡することが難しく、証拠も残りにくいため、発覚しても「一部関係者の暴走」として処理されがちです。
・法的空白地帯:景品表示法や公職選挙法の適用外であるため、倫理的に問題があっても法的責任を問うことが困難です。
◯世論誘導によるリスク
・政策判断の歪み:有権者が本来注目すべき政策内容や候補者の資質ではなく、操作されたイメージに基づいて判断してしまう可能性があります。
・対立の煽動:野党や特定候補者に対する否定的な印象が、事実に基づかず拡散されることで、健全な議論が妨げられる恐れがあります。
・民主主義の形骸化:選挙が「情報戦」ではなく「印象操作戦」と化してしまえば、もはや民意の反映とは言えなくなります。
政治的ステマは、その名の通り“ステルス(隠密)”な手法により、有権者の判断に密かに影響を及ぼし、あたかも世論が自然に形成されたかのように装います。こうした手法は、民主主義の基盤を静かに、しかし着実に蝕んでいく点において、極めて悪質であると考えられます。
最後に、ひとつ疑問を呈したいと思います。政治的ステマの問題は、果たして自民党だけに限ったものなのでしょうか。他の政党や政治団体においては、同様の行為が行われていないと言い切れるのでしょうか。
今回の件は、小泉陣営関係者によるリークによって明るみに出ました。しかし、組織の結束が強い政党や団体の場合、政治的ステマが行われていたとしても、それが表面化しにくい構造になっている可能性があります。組織的か否かにかかわらず、実態が見えにくいという点は、慎重に考慮すべきではないでしょうか。
したがって、他の政党や政治団体においても、同様の行為が存在しないのかという視点を持つことが、より公平で客観的な議論につながると考えます。