ギンリョウソウモドキ
- カテゴリ:勉強
- 2025/09/25 16:45:47
ニコットおみくじ(2025-09-25の運勢)

こんにちは!前線が南下する影響で、九州から近畿は日本海側を中心に雨や雷雨。
東北や北海道も日中は雨が降る。
関東甲信は晴れる。
沖縄は晴れ。
【ギンリョウソウモドキ】 銀竜草擬 Monotropa uniflora
Ghost Plant
Indian Pipe
☆ギンリョウソウモドキは、ツツジ科シャクジョウソウ属の多年草です。
<概要>
〇ギンリョウソウモドキ
@特徴
★草丈
ギンリョウソウモドキは草丈が約5~15cmになるツツジ科の多年草です。
☆開花期
日本では8~10月に開花します。
ギンリョウソウモドキは、
太く短い地下茎と根が密に絡まった球状の塊茎(かいけい)が地下にあります。
★塊茎
地下茎の一種で、地中にある茎の一部が澱粉(でんぷん)等の養分を備え、
塊状に肥大したものです。
ジャガイモやキクイモ等にあります。
塊茎から1~数本の太い地上茎を直立させ、
茎は分枝せず、鱗片葉(りんへんよう)を互生(ごせい)させます。
ギンリョウソウモドキは葉緑素を持たず、全体が透き通った白色です。
☆葉緑素
葉緑素「クロロフィル(Chlorophyll)」は、
植物や藻類に含まれる緑色の天然色素で、
光合成において重要な役割を果たします。
葉緑素は太陽光のエネルギーを吸収し、
水と二酸化炭素から有機物を合成するプロセスを助けます。
葉緑素は人間の血液の色素であるヘムと似た構造を持ち、
「緑の血液」とも呼ばれています。
■ヘモグロビンとヘム
◇ヘモグロビン
ヘムとグロビンから構成される赤血球のタンパク質で、
酸素を運ぶ役割を果たします。
ヘモグロビンは4つのヘム分子を持ちまして、
酸素を結び付けて運ぶことが出来ます。
ヘモグロビンは、
体内で酸素を肺から各組織へ運ぶ重要な役割を持っています。
◆ヘム
ヘムはヘモグロビンの一部であって、酸素と結合する力が強いです。
鱗片葉は長卵形で全緑、半透明で、茎の基部のものは小さくなります。
☆花
ギンリョウソウモドキの花は、茎先に1個を下向きに付けます。
花は長さが約1、5cmの筒形で白色ですが、
やや赤みを帯びることもあります。
■萼片(がくへん)
萼片は鱗片葉に似て、長楕円形です。
□花弁
花弁は萼片よりやや長く、先が円くなります。
■花柱(かちゅう)
花柱は先が蚊移出していまして、柱頭は暗紫色に染まります。
☆果実
ギンリョウソウモドキの果実は蒴果(さくか)で、小さな球形になります。
■蒴果(capsule)
複数の心皮(しんぴ)からなりまして、
果皮(かひ)が裂開して種子を放出する果実は蒴果と呼ばれています。
成熟した状態での果皮は普通乾燥していますが、
ホウセンカ(ツリフネソウ科)のように、
生きた組織の状態で裂開するものもあります。
@ギンリョウソウモドキの名前
ギンリョウソウモドキという名前は、
同科別属の植物「ギンリョウソウ(銀竜草)とほぼ同じ姿をしていることから、
ギンリョウソウモドキと名付けられました。
■ギンリョウソウ 銀竜草 Monotropastrum humile
Monotropastrum humile
ツツジ科ギンリョウソウ属の多年草です。
◇特徴
▲草丈
ギンリョウソウは草丈が約5~15cmになるツツジ科の多年草です。
△開花期
日本では4~8月頃に開花します。
ギンリョウソウは、
太く短い地下茎と根が密に絡まった球状の塊茎が地下にあります。
塊茎から1~数本の太い地下茎を直立させまして、
茎は分枝せず、鱗片葉を互生させます。
ギンリョウソウは葉緑素を持たず、全体が透き通った白色です。
鱗片葉は長卵形で半透明で茎の基部のものは小さくなります。
▲花
ギンリョウソウの花は、茎先に1個を下向きに付けます。
花は長さ約1、5cmの筒形で白色ですが、
やや赤みを帯びることもあります。
△萼片
萼片は鱗片葉に似て長楕円形で、花弁は萼片よりやや長く、
先が円くなります。
▲花柱
花柱は先が開出しまして、花柱は暗紫色に染まります。
△果実
ギンリョウソウの果実は液果(えきか)で、小さな球形になります。
▼液果
液果とは、広義には少なくとも果皮の一部が、
多肉質又は多汁質になっている果実ののことです。
この広義の液果は、多肉果と同義です。
広義の液果(多肉果)には、狭義の液果「漿果(しょうか)」とともに、
ミカン状果物、ウリ状果、ナシ状果、核果が含まれます。
一方、狭義の液果は内果皮(ないかひ)や中果皮(ちゅうかひ)とともに、
多肉質又は多汁質になっている果実のことでありまして、
この狭義の液果には漿果や真正液果と同義です。
人間が食用とする果実の中で、
ブドウ、柿、キウイフルーツ、ナス、トマト等は狭義の液果(漿果)です。
広義の液果は普通多肉質・多汁質の部分が、
鳥や哺乳類の食糧となって食され、
種子が排出されることで、種子散布されます。
◇名前
ギンリョウソウという名前は全体が銀白色に輝いて見えまして、
鱗のような鱗片葉と先端の筒形の花を、
銀色の龍に見立てたことから名付けられました。
又、葉緑素が無い為、キノコを連想しまして、
暗い林内に頂が垂れて開く草姿から、
白衣を纏(まと)った幽霊に見立てた、
「ユウレイタケ(幽霊茸)の別名もあります。
@ギンリョウソウモドキと菌類の関係
ギンリョウソウモドキは、かつて「腐生(ふせい)植物」と呼ばれまして、
腐生植物としてはもっとも有名な植物の一つです。
ギンリョウソウモドキは森林の林床に生えまして、
周囲の樹木と外菌根(がいきんこん)を形成して共生する菌類と、
モノトロポイド菌根を形成しまして、そこから栄養を得て生育しています。
問題 ギンリョウソウモドキは菌類に寄生しますが、
かつて???から栄養を得ていると思われていましたがありません。
???に入るかつてギンリョウソウモドキが???から得ていたとされる、
次の文章の中の???に入る物質を教えてください。
ギンリョウソウモドキは直接的には菌類に寄生しまして、
間接的には菌類に共生する樹木が光合成により作り出している有機物を、
菌経由で得て、生育しています。
古くは周囲の???から栄養を得ていると思われていて、
そのように書いてある著作も多くありますが、
???から有機物を得る能力はありません。
1、昆虫
2、鉱物
3、腐葉土
ヒント・・・〇???は菌類の為であり、
ギンリョウソウモドキ自身が直接利用は出来ない
@???の特徴
・有機物が豊富
・微生物のすみか
・土壌改良効果
微生物の働きを通じて栄養分を植物が吸収しやすい形に変えます。
お分かりの方は数字もしくは???に入る物質をよろしくお願いします。





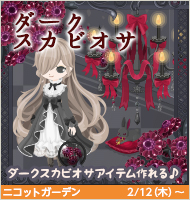














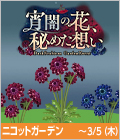





こんにちは!晴天の土曜日をお疲れ様です。
はい、おみくじですが「大吉」でした。
どうもありがとうございます。
そうですね、白いですし、おっしゃる通り個性的ですね。
はい、果実も個性的で名前も合っていますね。
問題の答えですが、3番の腐葉土が正解です。
素晴らしいですね!!どうもおめでとうございます(祝)
私はレモンを鉢植えで育てているのですが、土の下に腐葉土を敷いています。
割かし雑草が生えにくくなっています。
ギンリョウソウモドキは個性的なので、
発見したら即分かると思いました。
果実も個性的ですね。
名前も合ってますね。
答え 3