アカザラガイ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/09/24 17:01:16
ニコットおみくじ(2025-09-24の運勢)

こんにちは!暖かく湿った空気が流れ込み、
九州から近畿は太平洋側を中心に雷雨や雨の所も。
東海から北海道は晴れる。
沖縄は晴れ。
【アカザラガイ】 赤皿貝 Chlamys(Azumapecten)
farreri akazara Kuroda,1932
Akazara-scallop
☆アカザラガイは、
ホタテと同じイタヤガイ科カミオニシキ亜科カミオニシキ属に属する二枚貝で、
主に北海道南部から東北地方にかけて生息しています。
<概要>
〇アカザラガイ
@学名由来
★由来・語源
三陸地方の方言を岩川友太郎さんが亜種名としたものです。
□岩川友太郎(いわかわともたろう) さん
安政元年12月8日(1855年1月25日)-
昭和8年(1933年)5月2日
陸奥国弘前(現・青森県弘前市)出身で、
モースさんに師事して、近代的な分類額を学びます。
東京帝国大学(現:東京大学)卒で日本の教育者で動物学者です。
分類学的手法に基づく貝類目録を、
日本で初めて上梓(じょうし)したことでも知られています。
*上梓・・・日本語の文語的な表現で、
書籍や文章を「出版する」「世に出す」という意味です。
元々は中国の古典に由来し、
「梓」は気の名前で、昔はこの木を使用して版木を作り、
書物を印刷していたことから、
「梓に上る=出版する」という意味になりました。
岩川友太郎さんは、アカザラガイを命名した人物としても知られています。
岩川友太郎さんは日本海類学会の創設者であり、
貝類額の第一人者としての地位を確立しました。
■黒田徳米(くろだとくべい) さん
1886年10月17日ー1987年5月15日
兵庫県淡路島出身で、日本海類学会創設者で会長にもなりました。
植物学者・貝類学者で、日本の貝類研究の第一人者です。
日本で初めての貝類総目録を完成させ、
日本海類学会の創設者の一人でもあります。
発見した貝の新種は650種に及びます。
同郷の平瀬與一郎(ひらせよいちろう)さんの平瀬商店に、
丁稚奉公(でっちぼうこう)にあがり、
貝類の収集、後に分類に携(たずさ)わります。
◇平瀬與一郎 さん
安政6年11月11日(1859年12月4日)ー
大正14年(1925年)5月25日
民間の貝類研究家、貝類収集家、博物家で標本商です。
それまで欧米の研究者に依(よ)っていた、
日本の貝類額に手をつけた最初の日本人の一人で、
日本海類学史における最重要人物の一人です。
明治・大正期に精力的に研究活動を行いましたが、
生来病気がちであったことや、大学等の研究機関に所属せず、
全ての活動を私財を投じて行っていたこともあり、
ついには財力・体力とも使い果たして力尽きました。
日本産貝類の全貌究明を夢見ながら、
途半ばにして平瀬與一郎さんが残したのは、
貴重な標本類と「日暮れて道遠し・・・」の言葉でありました。
@地方名・市場名
★アカザラ、アカザラガイ
場所は北海道と青森県陸奥湾、青森市です。
☆サラガイ(皿貝)
場所は宮城県石巻市石巻魚市場さんです。
★アカジャラ(赤皿)
場所は青森県上北郡野辺地町(かみきたぐんのへじまち)です。
☆ババガイ、アカンジャラ、イタブ、ソデフリ
日本海類方言集 民俗・分布・由来(川名興 未来社)さんの文献より。
@生息域
★分布
北海道南部から東北です。
☆棲息
潮間帯から水深10mの現象域です。
@生態
★産卵期
夏です。
☆生活
岩等に足糸を絡ませて付着しています。
★体の特徴
アズマニシキの地方形です。
□貝殻
茶褐色か赤色をしています。
■放射肋、鱗片
アズマニシキよりも弱いです。
□前耳
長いです。
@基本情報
アズマニシキの三陸に多い亜種です。
★地方(青森県等の産地)
北海道や岩手県、宮城県等で養殖されていますが、
量的には少なく、消費地での認知度は低いです。
□流通形態
主に地元消費や産直で販売しています。
■価格帯:1kgあたり、約800~1200円
・養殖ホタテよりやや安価です。
・地元では「アカジャラ」等の名で親しまれていて、
刺身や焼き貝として人気です。
☆東京都内の市場(豊洲市場)
ホタテガイに負けない味わいで、
イタヤガイ科の養殖貝として、もっと人気が出てもおかしくはありません。
■2025年7月の平均卸売価格(参考:アカガイ):1481円/kg
・これはアカガイ(赤貝)の価格ですが、
アカザラガイも同程度か安価です。
・豊洲市場では流通量が少なく、希少性がある為、価格が安定しにくいです。
・飲食店や高級スーパーでは、
1個あたり、200~300円前後で販売されることもあります。
*アカザラガイの価格はアカガイとホタテガイと比較されることが多く、
季節や漁獲量によっても変動します
☆珍しさ
養殖物ですので、出荷時期の秋から冬には入手が可能です。
ただし、出荷量が少ないですので、かなり探す必要がありそうです。
@水産基本情報
★市場での評価
流通する総てが養殖されたもので、宮城県等の産地で消費されています。
あまり他の地域では出回りません。
関東等では、ホタテガイに比べて安いです。
☆漁法
養殖です。
★主な産地
宮城県や岩手県です。
@選び方
ホタテガイと同様の食し方をしますので、
貝柱の太っているもので、生きの良いものを選びます。
@味わい
☆旬
秋から春です。
★特徴
貝殻は硬いですが厚みはありません。
貝柱は大きいです。
熱を通しますと、貝柱以外は強く締まります。
@料理
・刺身 ・ワイン蒸し
・焼きアカザラガイ ・紐のセビチェ
・天ぷら ・バター焼き
・アヒージョ ・生殖巣「せいしょくそう(わた)」の煮付け
・味噌汁
問題 アカザラガイの中腸線(ちゅうちょうせん)についてですが、
次の文章の???に入る器官名を教えてください。
〇中腸線
???の一部であり、胃や肝臓に相当する機能を持つ器官です。
貝類の中腸線は栄養の吸収や〇〇だけに関わるだけではなく、
有害物質の蓄積部位としても重要です。
@中腸線について
〇〇腺ともいいまして、殻長近くにあります。
イタヤガイ科の中腸線についてですが、
例えばホタテガイ等のカドミウムの存在が問題になっている為、
アカザラガイの中腸線のカドミウム量は不明ですが、
基本的には取ってから料理をします。
1、呼吸器官
2、消化器官
3、循環器官
ヒント・・・〇〇〇盲嚢
〇〇液の分泌、〇〇物質の吸収、
食物粒子の細胞内〇〇等の機能を持ち、
二枚貝の〇〇や吸収課程において多目的機能を有しています。
お分かりの方は数字もしくは???に入る器官名をよろしくお願いします。





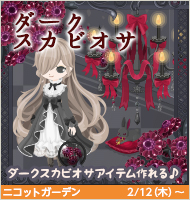














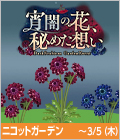





こんにちは!度々のコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、私の所も出回らないですね。
はい、そうですね、ゆっくりと食してみたいですね。
問題の答えですが、2番の消化器官が正解です。
こちらも大正解ですね!!
どうもおめでとうございます(祝)
こうした貝類にはホルモンを活性化させるものもありますので、
適量、召し上がってみるのが理想ですね。
勿論何かの持病等がある場合は、医療機関の診断をあおいで、
食してよいのかを、お聞きしてみるのが正解ですね。
美味しそうですね~
答え 2