ハナビラタケ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/08/11 16:15:42
カブトムシを保護しました。
2025/08/11

| 保護した場所 | 大きさ | レア度 |
|---|---|---|
| ニコット山 | 5.8cm |  |
こんにちは!前線の停滞で全国的に雨となる。
九州から関東は大雨に注意。
東北は南部を中心に天気が崩れる。
北海道は所々で雷雨。
沖縄は晴れ。
【ハナビラタケ】 花弁茸 Sparassis crispa(Wulfen)Fr,1821
Sparassis latifolia
Cauliflower fungus
Cauliflower mushroom
wood cauliflower mushroom
☆担子菌門(たんしきんもん)ハラタケ網タマチョレイタケ目に属し、
ハナビラタケ科ハナビラタケ属に分類される大型のキノコの一種です。
<概要>
〇ハナビラタケ
ハナビラタケはハナビラタケ科ハナビラタケ属に属し、1科1属のキノコです。
@色・形
淡黄色から白色で、珊瑚状の形をしています。
@生息場所
夏から秋にかけてモミやマツの針葉樹の枯れた樹木の根元に発生します。
@幻のきのこ
自然界での発生量は比較的少なく「幻のきのこ」と呼ばれています。
@名称
和名は、宮城県仙台市付近で得られた標本を基に与えられたものです。
この標本は所在不明であり、
分子系統学的知見を踏まえた現代の分類学に照らした場合、
S.crispaに当たるのかS.latifoliaに該当するのかは不明です。
★属名Sparassis
「きれぎれに裂けた」という意味があります。
☆種小名crispa
「縮れた」又latifoliaは「幅広い葉」を意味します。
★日本における方言名
奈良県吉野郡十津川村周辺では「ツチマイタケ」と呼ばれています。
又、東北地方の一部(岩手県や秋田県等)では、
「マツマイタケ」の名で呼ばれています。
□ツチマイタケの方言名
山形県下ではオオムラサキアンズタケを指す場合があり、
チョレイマイタケやカラスタケ等に対しても用いられることがあります。
■マツマイタケの呼称名
地域により、ハナビラタケとは全く別種のニンギョウタケを指して、
用いられることがあります。
□その他の地方名
ハナマイタケやハナヤサイキンの名でも呼ばれています。
■英語圏
子実体の外観や色調に因み、ハナビラタケ属に属するキノコ類一般に、
Cauliflower fungus(カリフラワータケ、ハナヤサイタケ)や、
Cauliflowe Mushroom(カリフラワーマッシュルーム)の名を、
当てています。
@分布
・日本 ・中国
・ヨーロッパ ・北アメリカ
これらの地域に分布しています。
従来、日本国内では、
北海道や本州及び四国に産するとされていましたが、
S.crispaとS.latifoliaの二種が、
ハナビラタケの和名の素に混合されているのか否かについては、
今後の調査の必要性があり、これらがともに日本に分布する場合は、
その各々が日本国内でどのような分布を示すのかについても、
詳しく検討する余地があります。
尚、栽培用種菌の中にも、これらが混在する可能性が皆無ではありません。
☆S.latifolia
東アジアの亜熱帯から温帯を中心に広く分布し、
日本とタイ、中国から報告されている他、
ヨーロッパ(西ドイツ、スウェーデン、フィンランド)にも分布しまして、
これらの地域でも従来はS.crispaやS.brevipesと、
混同されていたといいます。
*東アジアの亜熱帯から温帯・・・マツ科の針葉樹が分布する地域
又、ロシア南部にも産すると推定されています。
尚、S.latifoliaは中国においては、
恐らく南部から北部へと分布を広げていったものであろうと、
考えられています。
標高1000mを超える深山に生えることから、
一目につきにくく「幻のきのこ」といわれています。
@形態
★子実体
始め歪んだ球状で、
細やかな縮緬(ちりめん)状の不規則な皺(しわ)に覆われています。
次第に個々の皺が伸長して薄い膜となった花弁状の裂片を無数に分岐させ、
根元の太い柄で集合した丸い塊状をなしまして、
生長すると全体が径10~30cmになります。
そして、大きなものは径40cmにもなります。
ここの裂片はクリーム色か黄白色で、老成すると黄土色になります。
その縁は皺状に縮れるとともに、
しばしば不規則な鋸歯状に裂けます。
子実体の基部は特に箆(へら)状ないし、短い円筒状をなしまして、
宿主の材につながりますが、その長さや大きさは不定です。
肉は薄く、鮮時には柔軟で弾力のある肉質でありますが、
乾くと硬い角質となり、傷つけても変色もせず、
味も匂いも温和で特徴的なものはありません。
個々の裂片が直立した場合には、
胞子を形成する子実層「しじつそうhymenophore)が、
裂片の両面に発達しますが
裂片の水平の場合には、下側にのみ胞子が作られます。
☆胞子紋
白色を呈しまして、胞子は卵形ないし楕円形で平滑です。
そして、無色かつ薄壁でしばしば油滴を含みまして、
ヨウ素溶液で染まりません(非アミロイド性)。
シスチジアはなく、子実体を構成する菌糸は細く、
その壁は薄く、隔壁部にはかすがい連結を備えています。
■シスチジア cystidia
キノコの組織内に認められる不稔性の異型細胞を総称する用語です。
シスチジアの無い種や縁シスチジアと側シスチジアの形質が違う、
種等があり、キノコの同定では重要です。
日本語では一般に嚢状体(のうじょうたい)の語が当てられます。
□かすがい連結 clamp connection
分裂後の菌糸の隔壁の外側には、
片方に小さな膨らみが見られることがありまして、
このような構造をかすがい連結といいます。
菌糸の隔壁にこれが見られれば、その菌糸は二核菌糸であると判断出来ます。
それが子実体内部の菌糸でないならば、
その菌はまず担子菌類とみて間違いありません。
問題 本日は山の日で、登山家の間では美味しいと評判のハナビラタケです。
ハナビラタケは色々な料理に用いることが出来まして、
煮物や汁物等には、お出汁としても利用出来ます。
又、茹でますと、モチモチ・コリコリとした食感が楽しめます。
このハナビラタケに含まれる成分についてですが、
次の文章の???に入る栄養素名を教えてください。
ハナビラタケに含まれる有効成分の代表的なものは、
β-グルカンという物質です。
この物質は健康維持に役立つ成分として注目を浴びていまして、
キノコNO1の含有量を誇っています。
さらにグルタミン酸や???等のアミノ酸も多く含まれています。
1、グリシン
2、アスパラギン酸
3、システイン
ヒント・・・〇??? 野菜の〇〇〇〇ガスに含まれている
神経伝達物質になることや、
疲労回復、肝臓の保護等、様々な効果があるといわれる成分です。
お分かりの方は数字もしくは???に入る栄養素名をよろしくお願いします。


















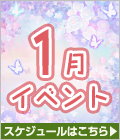








こんばんは!お忙しいところ、コメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、花束ですね。
そうですか、想像以上でしたか。
問題の答えは、2番のアスパラギン酸です。
大正解です!どうもおめでとうございます(祝)
アスパラガスを使用した冷製スープは、フランスではとても人気なのですよ。
そして、昨日冷やし中華にハナビラタケを具材に使用しました。
チゲスープにも入れました。
どちらの料理にも合いますので、使用してみるのはいかがでしょうか?
本日もお天気が不安定な所が多いようですね。
どうか気圧の変化によって、体調を崩されないようにお過ごしくださいませ。
想像以上でした。
答え 2