ネコノメソウ
- カテゴリ:占い
- 2025/03/27 15:20:36
ニコットおみくじ(2025-03-27の運勢)

こんにちは!低気圧が接近し、全国的に雨。
九州は終日、中国から北海道は午後から夜にかけて徐々に降り出す。
沖縄は曇りのち雨。
広い範囲で夏日となる。
【ネコノメソウ】 猫の目草 Chrysosplenium grayanum
Golden Saxfrage Chrysosplenium
☆ユキノシタ科ネコノメソウ属の多年草です。
<概要>
〇ネコノメソウ
ネコノメソウは湿った場所に自生する山野草です。
自生地には北海道の「釧路湿原」も含まれ、
広い場所で群生する様子は美しい緑の絨毯(じゅうたん)のように見えます。
@釧路湿原国立公園 温根内ビジターセンター さん
住所 :北海道阿寒郡鶴居村温根内(あかんぐんつるいむらおんねない)
電話番号:0154-65-2323
釧路市の市街から道道53号線を鶴居方面に走り、
釧路市湿原展望台を過ぎ、鶴居村に入ると、
道道脇に大きな駐車場が現れます。
駐車場から木立の中の木道を降りて行くと、
約3分程で温根内ビジターセンターさんに到着です。
明るくて解放感のあるビジターセンター内には、
釧路湿原や湿原で見られる動植物についての展示があります。
入り口近くには幾つものエゾシカの角も置いてあり、
自由に触れることも出来ます。
又、ここは釧路湿原の中を歩くことが出来る、木道のベース基地でもあります。
清潔なトイレも完備されています。
★温根内ビジターセンター さん 探勝歩道周辺の自然情報
ネコノメソウはミズゴケ湿原に生息しています。
鴨居軌道跡の湧水で見られます。
□北海道開拓を支えた鶴居村営軌道
釧路湿原の北西部に位置する鴨居村は、
大正元年(1921年)に開拓団の移住が始まりました。
大正12年(1923年)関東大震災の発生後、
救済を目的とした入植者が参加し、
北海道庁は根室本線新富士駅から鴨居村まで、
「殖民軌道(しょくみんきどう)」の敷設を計画します。
昭和4年(1929年)に馬鉄が開通し、
釧路市への人の移動や物資の運搬等、鶴居村の発展に重要な役割を果たし、
昭和29年には国から移管されまして、
「鶴居村営軌道(簡易軌道)」となりました。
この頃から道路整備が急速に進みまして、
定期バスの運行が始まったこと等から、
昭和43年に運行歴40年を数え、その歴史に静かに幕を降ろしました。
◆鶴居村営軌道の現在
「釧路湿原探勝路」として活用されています。
釧路湿原探勝路の北側にある「温根内木道」を歩きますと、
低層湿原の「ヨシ・スゲ湿原」と高層湿原の「ミズゴケ湿原」、
「ハンノキ林」等の植生が一度に見られます。
6月初旬に訪れると・・・
・エンコンソウ ・ヤチボウズ
・ヒメカイトウ ・ハナタネツケバナ
・ミツガシワ ・ワタスゲ
・ツマトリソウ ・イソツツジ
これら等の植物や、エゾハルゼミと出会うことが出来ます。
◇鶴居村ふるさと情報館 さん
酪農とタンチョウの里鶴居村をテーマに、
酪農の歴史と展望、鶴居村の軌道の歴史等が紹介されています。
▲屋外展示
昭和30年代に「鶴居村営軌道」で活躍したディ―ゼル機関車と、
自走客車(ディ―ゼルカー)が見学出来ます。
◇北海道の簡易軌道
大正末期から昭和40年代の約50年間、北の大地の開拓を支えまして、
入植者の生活に欠かせない存在であったことから、
次世代に伝える開拓遺産として「北海道遺産」に選定されています。
ネコノメソウは隙間無く、密になって生えることが多く、
地表を覆うようにして自生地を増やしていきます。
花の近くに付く苞葉(ほうよう)と呼ばれる小さい葉と、
下側に付く大きな葉の色の違いによりまして、
鮮やかな緑色のグラデーションが生まれまして、
群生する場所はまるで緑の絨毯のようです。
@基本情報
★草丈
5~20cmです。
☆開花時期
4~5月です。
@原産地と分布
日本や朝鮮半島、ロシアが原産地で、山間や草原の湿った場所に自生します。
北海道や本州の他、九州の北部地域にも分布しまして、
上記に掲載したように、北海道では日本で一番大きな湿原に指定されている、
「釧路湿原」に自生しています。
@特徴
★葉
葉の大きさは約5~10mmで、卵のような形をしています。
葉は鋸歯(きょし)と呼ばれる切れ込みがありまして、
葉がモコモコと山になっています。
□苞葉
花近くの苞葉は鮮やかな黄緑色で、
下の葉は緑色で、葉には僅かに厚みと艶があります。
■ランナーと呼ばれる親株から伸びる茎
小株が付きまして、
子株からも茎が伸びて、地面を覆うように成長していきます。
☆花
苞葉に囲まれた中央部分に、約2mmの小さな花が密集していきます。
花には花弁が無く、
代わりに花弁のような形をした萼裂片(がくれつへん)が4枚ありまして、
萼裂片の中に雌蕊2本と雄蕊が4本あります。
■花色
苞葉と同じく、黄緑色が鮮やかです。
@果実
果実は鶏の嘴(くちばし)のような形で、
果皮が乾いてくると、中央から縦に裂ける「蒴果(さくか)」になっています。
果実の中には茶褐色の小さな種が無数にありまして、
降雨の衝撃によりまして、種が外へ飛散します。
@名前の由来
裂けた果実の様子と、
明るい場所で瞳孔を細めた猫の目が似ていることが由来になっています。
@ネコノメソウの種類
☆ツルネコノメソウ(蔓猫の目草) Chrysosplenium flagelliferum
F.Schmidt.
Chrysosplenium flagelliferum
■ユキノシタ科ネコノメソウ属に分類される多年草の一種です。
◇特徴
湿地や渓流、湖畔沿い等の場所に自生しまして、多湿を好む植物です。
日本では近畿地方や四国に分布しまして、
4~5月に開花時期を迎えます。
開花後はランナーが親株から精力的に伸びて、子株を増やしていきます。
その他、ハナネコノメソウ(花猫の目草)もあります。
問題 上記に書かせていただきました、殖民軌道からです。
殖民軌道は、昭和4年に雪裡線(せつりせん)28kmが開業しまして、
幌呂線(ほろろせん)、途中の下幌呂から上幌呂15、4kmが、
開業しました。
*雪裡線・・・新富士~中雪裡間
終点の中雪裡は、現在の鶴居村の中心地辺りです。
次の文章の中の〇に入る動物名を教えてください。
当初は〇がトロッコを牽(ひ)く、旅客用の〇鉄で、
レール幅が762mmです。
昭和17年(1942年)雪裡線に自走客車が走行し始め、
所要時間が2時間に短縮されました。
*自走客車・・・バスのボディーを改造した本道最初の木炭カー
1、馬
2、牛
3、羊
ヒント・・・〇鶴居どさんこ牧場 さん
日本に8種類いる在来〇の一つで、乗〇を楽しめる牧場です。
お分かりの方は数字もしくは〇に入る動物名をよろしくお願いします。





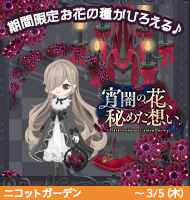

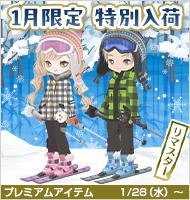












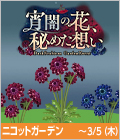





スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうでしたか、どうしても猫の目に見えませんでしたか。
そうですね、リアルでゆっくり観ると或いはの可能性ですね。
少しこういったものは、その人の物の見方の感性も関係していそうですよね?
どうしても猫の目に見えませんでした(笑)
リアルで見ると違うのでしょうね。
ミオティカさん、かげねこちゃん、どうもお疲れ様です。
ミオティカさん、はい、こういった植物があるのですよ。
かげねこちゃん、そうですか、ヒントで分かりましたか。
どうもありがとうございます。
問題の答えですが、1番の馬になります。
素晴らしいですね!!どうもおめでとうございます(祝)
お二人共、イベント開始後で、
大変多忙なところ、こうしてありがとうございました。
疲労のあるはずです。
どうかゆっくりとおやすみくださいませ。
ヒントで分かりました。ありがとうございました。
1、馬
ですね。
こんな名前の植物があるんですね(*ΦωΦ)シャー