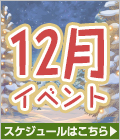コーデ記録~黒95-3
- カテゴリ:きせかえアイテム
- 2025/02/24 01:53:43
陰陽寮に新人が入った。
我々、陰陽師の仕事は、どちらかと言えば裏方。
パフォーマンスとして派手な見世物をすることもあるが、
そういった事は上の方(身分も役職も)がやることであり、
我々は日々、地道な仕事をこなしている。
主に暦関係で。
だが外回りもないではない。
怪異の原因を調べるため、現地に赴くこともある。
今回は新人と組む。
冬の都は底冷えがする。
粉雪が舞う夜も更けた道を進み、
待ち合わせの場所で新人と落ち合った。
が。
おいっ、その恰好はなんだ!
耳に首に腕にもふもふの毛皮で埋もれやがって!
「何と言われても、これだけ冷えるんですから、
毛皮のひとつやふたつないとやってられませんよ。
毛皮もなしに夜の調査とか、先輩はすごいですねー」
よく見ると異国渡りの短靴も履いていないか、お前。
俺なんか素足に草履だぞ?
ああもう、自由すぎる新人の面倒なんて放り出したい!
こうなりゃ背中に温熱の符を貼ってやる。
新人、お前には教えんからな!
なんとなく、こんな話(?)が浮かんだので。
黒95の第三弾は「陰陽師L」。
変形の狩衣に、下は袴かな? 膨らんでない。
あれ、紐で縛ってバルーン状にしているんだ。
形はきれいなので毛皮の小物を足してみた。
新人ちゃんはまだ成人ではないのだろう。
成人してたら頭に烏帽子がないと。
被ってないと裸よりはずかしいらしいぞ。
平安装束の足元は沓。
ただ身分が低いと多分草履だったんじゃないかと。
そして夏の背景を冬にする暴挙w
この背景のモデルは法観寺の五重塔なので、
平安時代にはもう建ってたはずでセーフ。
ただし。
きっとこのあたりには人家はなかったろうな。
鳥辺野も近いし。死体遺棄場。
清水寺も近いので、一寸法師で参拝のお姫様が襲われるのも、
まあ不思議じゃない立地。
「源氏物語」なんかで垣間見られる平安時代の生活。
でもそれって結局貴族階級のもので、
庶民の生活を私はほとんど知らない。
ほら、庶民、残るような文学とか書けないし。
貴族視点のものしか残っていないという。
そして着るものも家も。
貴族の邸宅ですら寒そうなんだよね、
平安時代って。
きっと塗籠が一番あったかい。
平安装束とかに興味持ったのは人形のせい。
人形にお雛様させたくて。
で、知った驚きの事実。
狩衣とかも、縫ってるより貼ってる方が多いとか、
袖口に通されている紐は、紐通しとかなく、
ぶっ刺してるとか。
当然、今のように良い針の糸も、
そして布もなかったはずで。
そうと知っていても、
絹糸をみすや針に通して正絹で人形の装束
縫ってるんだけどねw
いいの。
人形の衣装に時代考証はそこそこで。
だから大河の衣装とか建築とか
そのあたりはすごく気になるんだが、
去年の「光る君へ」だっけ?
内容はどうでもよくて見てないけど
(そもそも十年以上まともにTV見てない。
というか、今現在我が家にはTVが無いのだが)
美術の設定本があったら欲しいと探したがなかった。
家にある『六条院の生活』の方が使える資料だったよ……。