伊勢神宮祈年祭
- カテゴリ:勉強
- 2025/02/17 00:35:20
こんばんは!17日(月)は、
北日本や北陸から山陰では雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。
日本海側を中心に大雪に警戒してください。
その他の地域は概ね晴れますが、
東海では所によりにわか雨やにわか雪がありそうです。
【ゴシックコーデ/コーデ付き日記投稿イベント】
A、ダークブリ―スト(潔白の司祭)です。
【伊勢神宮祈年祭】 いせじんぐうきねんさい
☆伊勢神宮祈年祭とは「としごいのまつり」ともいわれ、
毎年2月17日に伊勢神宮さんだけではなく、
全国の神社で行われるお祭りです。
<概要>
〇伊勢神宮祈年祭
日本では古くから五穀豊穣を願ったり、
収穫を感謝する為の神事が行われています。
最も有名なのは毎年11月23日に日本各地の神社で行われる「新嘗祭」ですが、
新嘗祭と同じように日本各地で行われる神事の一つに、
「祈年祭」というものがあります。
@新嘗祭(にいなめさい)
新嘗祭はその年の豊作を祝うお祭りです。
・しんじょうさい
・にいなめのまつり
このようにも呼ばれ、
毎年11月23日に天皇陛下が神々に豊作の感謝を伝える他、
全国各地の神社でも祝いの祭りが開催されます。
★天皇陛下が行うこと
神々にその年の収穫物を御備えし、
後に自らもそれをお召し上がりになられるという儀式が挙げられます。
□収穫物
米をはじめとする五穀が納められます。
五穀の穀物で、明確な規定はありませんが・・・
・稲 ・麦
・栗 ・大豆
・小豆
これらが代表例とされることが多いようです。
★大嘗祭(だいじょうさい)
天皇陛下が即位して最初に行う新嘗祭を、
通常とは別に大嘗祭と呼ぶことがあります。
大嘗祭は「おおにえのまつり」とも呼ばれていまして、
天武天皇の頃から新嘗祭とは別に行われるようになったといわれています。
律令制の時代になりますと、
天皇が代わる毎に大嘗祭が行われるようになりました。
応仁の乱の時期になりますと実施が困難になりますが、
江戸時代になり、世の中が平和になりますと再度実施されるようになります。
そして・・・
1738年の桜町天皇の即位時から都度行われるようになりまして、
現代に至っています。
☆祈年祭:毎年春に豊作を祈る為に行われる祭り
新嘗祭がその年の方策を感謝する一方で、
祈年祭は春にその年の豊作を祈る為に行われるという違いがあります。
祈年祭は天武天皇の時代には行われていたとされていまして、
室町時代になりますと行われなくなりますが、
明治時代になって再興され、現在は毎年2月17日に宮中で行われています。
祈年祭は「春祭り(はるまつり)」ともいいまして、
年の初めにお米をはじめとする穀物類の五穀豊穣を祈る神道のお祭りであり、
神社で行われるお祭りの中でも重要なものの一つです。
又、「としごいのまつり」の「とし」は稲のことを指しまして、
「こい(こい)」は祈りや願いのことを意味していまして、
「としごい」は五穀豊穣を祈るという意味になります。
お米や穀物類を作ることで生活が成り立っていた時代、
五穀豊穣を祈ることは国の安泰や繁栄を祈ることと同じと考えられていまして、
国家が行うお祭りとされていました。
現在、祈年祭は宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)の一つになっています。
@宮中祭祀
皇居にある宮中三殿において、
天皇陛下が国家と国民の安寧と繁栄を祈ることを目的に行う祭祀のことです。
*祭祀・・・感謝や祈りの為に、神仏及び祖先を祀ること
★宮中三殿
・賢所(かしこどころ)
・皇霊殿(こうれいでん)
・神殿(しんでん)
宮中三殿とは、神道の神を祀るの総称です。
@祈年祭の起源
農民が豊作を齎(もたら)すと信じていた、
「田の神」だったといわれています。
そのお祭りが天武天皇の時代に国家祭祀として、
日本各地の神社で行われたという記録が残っています。
*天武天皇・・・第40代天皇(在位:673年~686年)
*国家祭祀・・・国が行う祭祀
☆奈良時代(710年~794年)
・五穀豊穣
・国家安泰
・天皇安泰
これらを祈るという儀式の形が定まりました。
★平安時代(794年~1185年)
天照大御神(あまてらすおおみかみ)様に、
天皇が豊作を祈願する祭祀となりました。
☆室町時代(1336年~1573年)
室町時代の戦乱期に廃絶してしまいます。
★明治時代(1868年~1912年)
明治時代に重要な国家祭祀として復活しまして、
宮中ではなく、全国の神社で祈年祭が行われるようになりました。
第二次世界大戦後は、GHQの占領政策によりまして国家神道が廃止されます。
*GHQ ・・・連合国軍総司令部
*国家神道・・・国として神道を信仰すること
「祈年祭」は国家祭祀ではなく、天皇家が行う宮中祭祀になりました。
国家祭祀ではなくなっても、
年の初めに五穀豊穣を祈るお祭りは神道ではとても重要なものですので、
「祈年祭」は現在も多くの神社で続けられています。
宮中祭祀は天皇の国事行為ではなく、
皇室の私的行事として扱われていまして、祈年祭も例外ではありません。
国事行為とは、
天皇が行うものとして、日本国憲法に規定された行為のことです。
@2025年の祈年祭
祈年祭は元々立春である旧暦2月4日に行われていましたが、
旧暦から新暦へ改暦後の明治6年(1873年)に、
毎年2月17日に固定されました。
よって、2025年の祈年祭は2月17日(月)です。
地域によりまして、3月や4月になってから「春祭り」として、
五穀豊穣を祈る等、農耕に関わる神事として行う神社もあります。
*農耕・・・主に稲作
@伊勢神宮さんの祈年祭 2月17日(月)
☆開催時間
□外宮(げくう)
「大御饌(おおみけさい)」:2月17日 16:00
■奉幣(ほうべい、ほうへい)
2月17日 7:00
ただし、外宮の「大御饌」は参拝時間外につきまして、参拝不可です。
☆会場
伊勢神宮(外宮)
★住所
三重県伊勢市豊川町279
☆電話番号
0596-24-1111(神宮司庁)
★料金
無料
☆アクセス
■公共
・JR伊勢市駅側出口から外宮表参道一口までは徒歩約5分
・近鉄宇治山田駅から徒歩約7分
□お車
伊勢自動車道「伊勢西IC」から県道32号線を、
伊勢市街方面へ約2km(約5分)
問題 次の文章の〇〇〇〇に入る言葉を教えてください。
おさらいです。
祈年祭は春の耕作始めにあたりまして、
〇〇〇〇を祈るお祭りで「としごいのまつり」とも呼ばれています。
「とし」は稲の美祢(みね)でありまして、「こい」は祈りや願いで、
お米を始めとする〇〇の豊かな稔(みの)りを祈ることを意味します。
稲の育成周期が、日本人の一年といえます。
1、五穀豊穣(ごこくほうじょう)
2、舐糠及米(しこうきゅうまい)
3、米穀菜蔬(べいこくさいそ)
ヒント・・・〇〇〇〇〇祭り ウカノミタマという食物の神が崇められる
神社等で豊作を祈る祭りであり、
穀物が豊かに実ることを願う祭りです。
お分かりの方は数字もしくは〇〇〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。





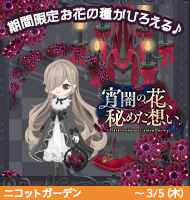














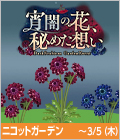








そうですね、真夏の気温が気になりませんか?
そうですね、はい、備蓄米が放出されましたね。
そうですね、お米は主食の方が多いですから、
安くなり、手に入りやすくなることを心よりです。
備蓄米をやっと放出になりましたね。
お米が安く手に入りますように(。-人-)☆
こうしてコメントとお答えをありがとうございます。
かげねこちゃん、どうもお疲れ様です。
そうですか、調べないで、ヒント通りにおさらいをしてくださりましたか。
お疲れのなか、どうもありがとうございます。
問題のお答えですが、1番の五穀豊穣(ごこくほうじょう)が正解になります。
かげねこちゃん、しっかりとヒント通りにおさらいをなされた結果ですね。
その素晴らしいおさらいという努力と行動、感銘を覚えました。
かげねこちゃん、これから陽射しが無くなり、
冷えてくる恐れが高いですので、体調を崩さないように暖かくしてお過ごしくださいませ。
今週もどうぞよろしくお願いします。
今回は調べないで、ヒント通りにおさらいをしたつもりですが・・・???
1、五穀豊穣(ごこくほうじょう)
では如何でしょうか???