七草の日
- カテゴリ:美容/健康
- 2025/01/07 01:08:15
こんばんは!7日(火)は、
北日本から西日本日本海側では雪や雨が降り雷を伴う所もある見込みです。
東日本太平洋側は明け方頃までは雨の降る所がありますが、
次第に晴れ間が広がる見込みです。
西日本太平洋側は雲が広がりやすく所によりにわか雪やにわか雨があるでしょう。
南西諸島は晴れたり曇ったりとなる見込みです。
【2025年の抱負は?】
A、昨年の26日に体調を崩してしまいましたので、
今年は1年間体調を良く過ごしていきたいです。
【七草の日】 ななくさのひ
☆七草粥は毎年1月7日ちょうどお正月が終わり、
落ち着いてきたタイミングで食される「春の七草」を用いたお粥のことです。
<概要>
〇七草の日
1月7日は七草の日です。
七草の日に七草を入れた七草粥を食す習慣は、
上巳(じょうし)の節句(桃の節句)や端午の節句等の五節句の一つです。
@五節句に食すもの
七草粥が「人日(じんじつ)の節句」の食べ物であるなら、
その他の節句ではどんな料理があるのか?
★桃の節句(3月3日)
雛祭りとして知られていまして、
ちらし寿司や蛤(はまぐり)等を食します。
☆端午の節句(5月5日)
子供の日として祝われ、粽(ちまき)や柏餅等を食します。
★七夕の節句(7月7日)
そうめんを食す習慣があります。
☆重陽(ちょうよう)の節句(9月9日)
菊の節句、桃の節句ともいいまして、栗ご飯や秋茄子を食します
年末年始やお正月を終え、
胃や身体を労(いた)わる為に七草粥を食し、
今年一年の無病息災を願う行事です。
「七草粥の日」は・・・
・人日の節句 ・七草の節句
・七草 ・七草の祝い
これら等と表現される時もあります。
@七草粥
1月7日に「七草」を入れて炊いたお粥を食すことで、
「七草粥の日」や「七草の日」といわれています。
・セリ ・ナズナ
・ゴギョウ ・ハコベラ
・ホトケノザ ・スズナ
・スズシロ
これぞ七草という覚え歌があります。
★春の七草の覚え方
「芹なずな御形(ごぎょう)はこべら仏の座、
すずなすずしろこれぞ七草」
このような四辻左大臣さんの歌になぞられたものです。
《四辻善成(よつじよしなり)》さん
嘉暦元年(1326年)-応永9年9月3日(旧暦)1402年9月29日
南北朝時代から室町時代にかけて活躍しました、
希代の公家で学者で歌人です。
順徳天皇の曾孫にあたる四辻善成さんは皇族としての血筋を持ちながらも、
波乱に満ちた生涯を送ることになります。
〔華麗なる出世の階段〕
摂関家で二条良基さんの養子となりました善成さんは、
康永2年(1343年)に異例ともいえる速さで従四位下に叔任され、
左近衛少将にも任じられます。
これは三世王でありながら、
王族として近衛少将に任官されたという、特例中の特例です。
その後も善成さんの昇進は目覚ましく、
文和5年(1356年)には従三位に叔任されまして、
源朝臣姓を与えられまして臣籍降下します。
臣籍降下後も皇族に準ずる待遇を受けまして、
「四辻宮」と称されました。
延文年間(1358年~1361年)には正三位、
左近衛中将へと昇進します。
さらに康安元年(1361年)には従二位、
貞治2年(1363年)には正二位と、
順調に出世の階段を駆け上がります。
貞治6年(1367年)には参議を飛ばして権中納言に任ぜられる等、
まさに摂関家の子弟に匹敵する程の速さで出世を遂げました。
応安3年(1370年)には権大納言に昇進しますが、
翌年にはこれを辞任します。
足利義満公の台頭後も、善成さんの昇進は止まりません。
永徳元年(1381年)には従1位、
嘉慶元年(1387年)には准大臣に叔任されまして、
応永元年(1394年)には内大臣に任じられます。
しかし、僅か半年後には内大臣を辞任します。
そして応永2年(1395年)7月には左大臣に昇進しますが、
これも僅か1カ月で辞任しまして、8月29日に出家しました。
最終官位は前左大臣従一位、法名は常勝さんです。
出家を決意した善成さんは親王宣下を望みましたものの、
斬波義将さんの反対によりまして、果たせなかったと伝えられています。
出家後は嵯峨(現:京都市)で余生を過ごしました。
応永9年(1402年)9月3日、77歳でこの世を去りました。
☆七草粥を食す風習の由来
七草粥の起源は中国の節句といわれています。
古来の中国では新年の占いとして・・・
・正月の1日:鶏の日 ・2日:狛(犬)の日
・3日 :猪(豚)の日 ・4日:羊の日
・5日 :牛の日 ・6日:馬の日
このようにそれぞれの日にはその動物を占ったり、
その動物を殺めないように定めていました。
そして・・・
1月7日は人の日(人日じんじつ)として、
犯罪者等に対する刑罰等を行わないことにしていました。
★七種菜羹(しちしゅさいこう)
又、この日は中国の官吏(かんり)の昇進を決める日でもありまして、
朝食は「七種菜羹(しちしゅさいこう)」という、
七種の野菜を入れた羹(あつもの)=温かい汁物を食して、
立身出世を願ったとされています。
☆「七種粥」と「若菜摘み」
日本では2つの風習が元となっています。
■七種粥
1月15日の小正月にお粥を食す「七種粥」。
この七種は・・・
・米 ・粟(あわ)
・稗(ひえ) ・黍(きび)
・ミノ ・胡麻
・小豆
これら等を入れていました。
小豆粥として現在でも地方によりましては残っています。
□若菜摘み
年の初めに雪の間から芽を出した草を摘む習慣がありました。
問題 下記の百人一首の歌人名を教えてください。
百人一首にも有名な歌があります。
「君がため 春の野に出てて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつ」
新春に若菜を食しますと、
邪気を払って病気が退散すると考えられていました。
その頃は時期に採れる野菜を7種程入れていました。
地方によりましても異なっていたそれらの野菜は、
1360年頃室町時代に詠まれた歌です。
・芹 ・ナズナ
・ゴギョウ ・はくべら
・仏座 ・すずな
・すずしろ
これぞ七種とされています。
1、天智(てんじ)天皇
2、聖武(しょうむ)天皇
3、光孝(こうこう)天皇
ヒント・・・〇百人一首の15番である天皇の歌です。
830年~887年(天長7年~仁和3年)の第58代天皇です。
55歳の時に天皇に即位しまして、58歳で崩御されました。
容姿端麗で聡明、教養あふれる人物だったといわれていまして、
「源氏物語」の主人公・光源氏さんのモデルという説もあります。
お分かりの方は数字もしくは上記百人一首の15番の歌をお詠みになられた、
天皇陛下名をよろしくお願いします。





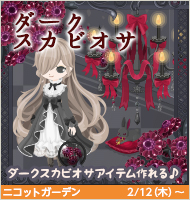














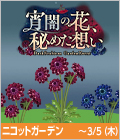





そうですか、お昼に七草粥を食されましたか。
夕食にシチューとパンとはご馳走ですね。
現在、お腹の調子はいかがでしょうか!?
まだ本調子でないようでしたら、ご無理をなさらずお過ごしくださいませ。
夕飯はまだお腹が本調子ではないらしく、
シチューとパンにしました(^q^)
かげねこちゃん、どうもお疲れ様です。
そうですか、調べてくださりましたか。
どうもありがとうございます。
問題ですが3番の光考天皇が正解です。
したがいまして、大正解になります。
凄いですね!かげねこちゃん、バッチリですよ!!
どうもおめでとうございます(祝)
難しい問題なのですが、流石ですね。
本日ですが、七草粥をなるべく食して、
一年間、病気をしないように願いながら、過ごしてまいりましょうね。
3.光孝天皇
でしょうか?