官庁御用始め
- カテゴリ:占い
- 2025/01/06 16:03:17
ニコットおみくじ(2025-01-06の運勢)

こんにちは!低気圧の接近や前線通過の影響で、
西日本は朝から、東日本と北日本は昼頃から雨の所が多くなる。
沖縄は晴れ。
寒さは和らぐ。
【官庁御用始め】 かんちょうごようはじめ
☆「日本大百科全書(ニッポニカ)」には、
「年の初めにあたり、年間の豊穣や繁栄を祈って行われる、
家業・生業に関する儀礼「事始めと呼ばれる」とあります。
さらに読み進めますと・・・
・舟祝い
・田打ち正月
・鍬入れ
これら等、行われる仕事内容によりまして、様々に呼ばれています。
■舟祝い 漁師さんの仕事始め(鎌倉腰越漁港)
神奈川県の鎌倉の腰越漁港では1月4日(8:30時から)、
漁師さんの新年行事「舟祝い」が行われます。
大漁旗や五色の吹き流しが建てられた各船で、「舟祝い」が執り行われます。
・本年の大漁
・航海の安全
・乗組員の健康
これらを祈念されます。
大漁旗を揚げた船の上からは参観者に向かいまして、
「みかん」が撒かれます(みかんの他に、お菓子も撒かれます)。
みかんは黄金色に似ている為、小金が1年間の漁によりまして、
返ってくるようにという願いが込められています。
9:30 相州神童太鼓
9:00 舟祝い(みかん撒き)
*記載の内容は例年のものですので、
実施時間等につきましては、確認をお願いします
みかん撒きが終わりますと、初船出が行われまして、
小動(こゆるぎ)神社さんと江の島に大漁と安全が祈願されます。
みかん撒きに先立って行われるのは、相州神童太鼓の演奏です。
福笹は本覚寺さんの「鎌倉えびす」のものです。
◇新年の鎌倉・・・海の行事~
・船おろし ・潮神楽
1月2日 1月11日
(坂ノ下・材木座) (材木座)
・汐まつり ・鎌倉の海
1月11日
(坂ノ下)
坂ノ下海岸と材木座海岸では、1月2日に「船おろし」が行われています。
1月11日には材木座海岸で「潮神楽」が、
坂ノ下海岸で「汐まつり」が行われます。
▲腰越漁港
腰越漁港は小動岬の西側に隣接する漁港です。
腰越は江戸時代には「鎌倉五ヶ浦」と呼ばれた漁村でした。
住所:神奈川県鎌倉市腰越2-9-1
アクセス:江ノ島電鉄さん「腰越駅」より徒歩約3分
『鎌倉五ヶ浦』
・材木座 ・坂ノ下
・腰越 ・片瀬
・江ノ島
腰越漁港は小動岬の西側に隣接する第1種漁港です。
神戸川の先は腰越海岸です。
毎月第1・第3木曜日には朝市が開催されまして、
その日獲れた新鮮なシラス等の水産品が販売されます。
*午前10時から正午まで
漁協組合の販売所で2014年4月から始まったという、
大人気の「朝どれフライ」は、
その日の朝獲れた魚を調理したものです。
*午後1時から販売
*12月の朝市は第1木曜日のみ
□田打ち正月
岩手県の「田植え踊り」は・・・
・大沢田植踊り
・山屋の田植踊
・小田島田植踊り
これらが有名です。
「予祝芸能(よしゅくげいのう)」が由来といわれていまして、
「予祝儀礼」ともいわれています。
「あらかじめ(予)」祝う「前祝い」と、
「大衆的娯楽(芸能)」を兼ねた行事で、
「農耕儀礼」の一種だといわれています。
実際に収穫するよりも前に祝うことによりまして、
豊作を祈願する行事で、天候不良や病気等による不作を防ぐ、
「除災」の意味合いも兼ねているといわれています。
「農耕儀礼」に関しては岩手の「田植え踊り」以外にも、
「田打ち正月」や「田遊び」等が有名です。
◆岩手の田植え踊りの由来
当時、広く開梱が進められていた時に、
田植え技術を伝える意味も兼ねて行われていたのも由来といわれており、
屋内の「庭田植え」と屋外の「座敷田植え」の2種類に分かれます。
伝承されていくうちに「中部型」のように、
様々な「型」が分かれていきました。
岩手だけでも・・・
・気仙 ・東磐井型
・胆沢(いざわ)形 ・和賀(わが)型
・中部型
これら等、5種類以上の田植え踊りが存在します。
岩手の「山屋の田植踊」や「大沢田植踊り」に関しましては、
「重要無形民俗文化財」として認められています。
・苗代作り
・田植
・稲刈
これら等の田植えや稲刈風景を順番に演じていきます。
・孫蔵
・弥十郎
・えんぶり
このように呼ばれる「舞台進行役」が存在しまして、
村や町の若者達を中心とした「早乙女」「奴」「あやとり」達が、
舞踏を始めます。
舞踏が始まりますと「一八」と呼ばれる、
進行役が励ましながら進んでいくのが特徴です。
□鍬入れ
地鎮祭とは、家を建てる際に工事の無事や安全を祈願する儀式のことです。
地鎮祭(じちんさい)と読む他に、
「ことしずめのまつり」と読むこともあります。
そんな地鎮祭に行われる儀式の中に、鍬入れという儀式があります。
この儀式のことを「地鎮の儀」といいまして、
この儀式は新築工事等の際に、儀礼的にその土地に鍬を入れることです。
昔の家を建てる為には・・・
①手の入っていない雑草だらけの土地を鎌で雑草を刈る
②桑で土を掘り起こす
③鍬で土地を平らに均して家を建てる為の土台を作る
この工程をしないと家を建てられないということから、
盛砂を均されていない土地に見立てて鍬を入れる動作を行う必要があります。
地鎮祭の鍬入れは手の入っていない土地に手を加えることを、
神様の前で行い、家を建てる許しを得る為の意味があります。
鍬入れの方法は用意した盛砂を鍬で掘る仕種を3回程度繰り返し、
左→中央→右の順番になります。
@仕事始め
12月28日(土)から1月5日(日)と9連休となる所もありますが、
2025年の「仕事始め」は1月6日(月)です。
問題 書道等の場合は「書き初め」ですが、
仕事は「始め」でしょうか?
1、同じ
2、始め
3、初め
ヒント・・・×仕事〇め
「仕事〇め」という表現は一般的には用いられません。
誤解が生じがちですが「〇め」は物事の「最初の出来事」を指し、
例えば新しいプロジェクトのスタート等が該当します。
〇仕事〇め
「〇め」とは何かが「開始されること」全般を意味しまして、
特に新年の業務再開等に使用される言葉です。
一般的に「仕事〇め」とは新年の業務開始日を指しまして、
企業や官公庁が新たな一年の業務を開始する日を意味します。
一方で・・・
「仕事〇め」として誤って使用されることがありますが、
これは新入社員が初めて仕事を行う日や、
年の初めに仕事を始める日という非公式の用法で、
辞書には記載されていない非公式な表現です。
@御用〇め
公務員や官公庁では、
新年の業務開始を「御用〇め」と称します。
お分かりの方は数字もしくは仕事ですが「同じ」なのか?
「始め」なのか?「初め」なのか?をよろしくお願いします。





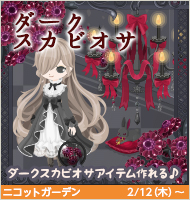














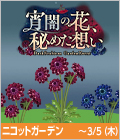






スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
おみくじですが「大吉」でした。
どうもありがとうございます。
ああ~、なるほど~、確かにみかんは衝撃や酸化から傷みやすいですね。
素晴らしい、読みですね。
問題ですが2番の始めが正解になります。
スズラン☆さん、大正解です。
どうもおめでとうございます(祝)
今年も体調に気をつけて、様々なものを始められてみるのはいかがでしょうか?
本日も寒さから、体調を崩さないようにご注意くださいませ。
みかんを撒くは、床に落ちたところが傷みやすいだろうなとか、
想像しました(笑)
答え 2