初荷
- カテゴリ:占い
- 2025/01/02 15:15:58
ニコットおみくじ(2025-01-02の運勢)

こんにちは!今日1月2日(木)は西高東低の冬型の気圧配置が続きます。
北日本日本海側では雪、北陸では雨が降り、風も吹く所がありそうです。
太平洋側の各地は穏やかな冬晴れが続きます。
沖縄も湿った空気の影響で雨の降る所がありそうです。
【初荷】 はつに
☆初荷とは年が明けて、
最初に工場や倉庫等、物流拠点から販売店へ向けて商品が出荷されることです。
*商品・・・製品
<概要>
〇初荷
@初荷の伝統とその歴史的背景
★初荷の意義
「初荷」とは新年が空けて最初に商家が行う仕事始めの際に、
荷物が出荷されることを指しています。
商業活動の再開を象徴する行事であり、
一年の商売繁盛を願う意味合いが込められています。
かつては江戸時代から続く伝統として、
問屋や商店が初売りと同時に新年の商い初めを飾り立て、
荷物を売り先に送り出していました。
これは・・・
新年の祝福と繁栄を願う日本独特の風習です。
初荷には商家の意気込みや一年の願いが込められていまして、
それを形に表したのがのぼり旗や飾り付けられた車や馬でした。
これらの装飾は商家の繁栄と幸運を祈る、
重要な役割を果たしていました。
□江戸の正月風景
江戸時代には現代のような曜日や休日感覚はなく、
正月と盆に加え、五節句や寺社の縁日を中心に仕事を休んでいただけです。
又正月2日は新年の顔合わせ的な要素も強く、
仕事は午前で終え、午後からは祝い膳を囲むことが多かったようです。
◆初日の出
江戸の正月は静かですが朝は早いです。
中でも「初日の出」を拝む人達は、月明かりの全く無い大晦日の夜道を、
目的地まで黙々と歩きました。
*月明かりの全く無い大晦日・・・大月籠(おおつごもり)・新月
当時、初日の出を迎える名所は・・・・
・芝浦 ・愛宕山
・神田 ・湯島
・深川洲崎堤防
これら等です。
いずれも海に面しているか、海の見える高台にありました。
◇新年の祝い
一方、町中(まちなか)は綺麗に掃き清められまして、
前夜遅くまで続いた喧騒が嘘のように全ての見世(店)は、
雨戸を締めまして、物音一つしない静けさの中で迎えました。
それでも・・・
初日の出を拝み終えた人達が家路に着く頃には、皆起き出しました。
家長を中心に若水(わかみず)を汲みまして、
その水で雑煮を煮、福茶(ふくちゃ)を飲んで新年を祝う為です。
▲若水
新年の最初に汲み上げる井戸水のことです。
江戸の水道は蛇口をひねると水が出るものではありません。
文字通り水の通る道、水路のことです。
四谷大木戸までは露天のままで、
そこから先は地下に埋設された木桶を通りまして市中を巡っていました。
木桶には所々に水を溜める枡が設置されまして、
地上と枡は井戸で繋がっていました。
その井戸から最初に汲み上げる水が若水です。
汲み上げた水は一旦瓶(かめ)に入れられまして、
必要の都度手桶で器に移して利用しました。
お正月にはこの手桶も新調して輪飾りをかけまして、
瓶から水を汲む場合は恵方に向かって汲むのが習わしでした。
△福茶
お茶に梅干又は結び昆布、或いは両方を入れたものです。
西日本各地では現在も広く行われていますが、
東京では絶えた風習のようです。
◆恵方参りと年籠・初縁日詣
新年の祝いが終わりますと、再び静けさが戻ります。
その後は、恵方参りや氏神への初詣に出かける者もありましたが、
多くは終日のんびり過ごしました。
当時は現在のような初詣習慣はなく・・・
・初子(大黒天様)
・初不動(不動明王様)
等への初縁日詣がいわば初詣のようなものでした。
△恵方参り
歳徳神「とくとくがみ(その歳の福徳を司る神で、
干支によって毎歳変わる)」のいる寺社へ参詣することです。
氏神への初詣は元来「年籠(としごもり)」でした。
家長が大晦日の夜から元日の朝にかけて、
氏神の所へ籠る(年を越えて籠る)ことです。
今年一年無事に過ごせたことへの感謝と、
新年の無事と平安をお願いする為でした。
これが大晦日の「除夜詣」と元日の朝の「元日詣」の2つに
分かれたのです。
除夜詣は、除夜の鐘突きに残りまして、
元日詣は初詣に変化したとされています。
尚、今のような氏神と全く切り離された初詣をするようになったのは、
明治半ば以降のことです。
その頃発達した鉄道各社が、
自社の経営する鉄道沿線にある寺社への誘客運動の一環として、
行ったのが最初とされています。
▲宝船売り
正月元旦もしくは二日に売り歩いていた「宝船売り」。
これを枕の下にひいて寝るといい夢が見れると信じていたものです。
七福神を乗せた船の周りに書かれてある文字は、
回文(前後どちらから読んでも同じ分)になっています。
「なかきよのとをのねふりのみなめさめさめなみのり
ふねのおとのよきかな
(長き夜の遠の眠りの皆目覚め波乗り船の音の良きかな)」。
発声は~・・・
「おたからお宝お宝初夢 吉夢福の夢 福夢見たいと願うから
枕の下に宝船 お宝お宝お宝」
このように言ってました。
尚宝船の刷り色は大抵赤色です。
余談ながら疫病神の刷り色も同じ赤色であったのが面白いです。
@初荷の変遷
初荷は元々は1月2日に行われることが一般的でしたが、
時代の流れとともに1月4日に行われることが多くなりました。
これは、官公庁や多くの企業が業務を開始する日に合わせたものです。
又、新年の営業開始とともに、新たな気持ちで一年の商いをスタートさせる、
意味があります。
@初荷と現代社会
初荷に際しては、商品の梱包や配送にも特別な注意が払われます。
これによりまして、一年の始まりに品質の高い商品を顧客に届けることで、
信頼と満足を提供することが出来ます。
問題 次の文章の中の〇〇に入る言葉を教えてください。
初荷には商家が新年に願う繁栄や成功が込められています。
これは商売がうまくいくことを祈る日本の商習慣でありまして、
新年を迎えるにあたっての祝福の意味があります。
商家は初荷を通し、一年間の商いに対する意気込みを示し、
顧客への感謝の気持ちを表現します。
これにより顧客との良好な関係を築きまして、
一年間続く商いの〇〇を固めることが出来ます。
1、戦略
2、基盤
3、方針
ヒント・・・〇事業〇〇
営利を目的として商品の販売やサービスの提供等の、
経済活動を営む組織が、
営利等を目的として組織を営むことを「事業」といいます。
元々「事業」とは「易経」からきています。
*易経・・・四書五経と呼ばれる儒教の経典の一つ
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。













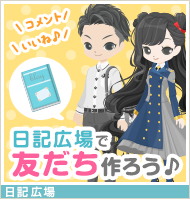






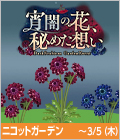






スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、日本人は働き者の方が多いですね。
問題ですが2番の基盤が正解になります。
そうですよね、悩みますよね。
昔から日本人は働き者だなと思いました!
答え 3かな?2も悩みました。