オミナエシ
- カテゴリ:占い
- 2022/10/15 15:41:54
ニコットおみくじ(2022-10-15の運勢)

こんにちは!九州から北陸、東海は晴れ。
関東と東北は上空に湿った空気が入り込みやすい。
北海道は雨や雷雨の所も。
沖縄は雨のち曇り。
【オミナエシ】 女郎花 Patrinia scabiosifolia
Golden lace
☆合弁花類オミナエシ科オミナエシ属の多年生植物です。
<概要>
〇秋の七草
秋の七草の一つに数えられていまして、万葉集の時代から愛されている花です。
〇広範囲に分布しますが沖縄県だけには咲かない花
オミナエシはンつから秋にかけまして、陽当たりの良い草原で見られる野草です。
真っ直ぐに伸ばしました茎の先に沢山の小さな黄色い花を咲かせるのが特徴です。
〇別名
・ハイショウ(敗醤)
・アワバナ(粟花)
〇分類
・山野草
・多年草
〇原産地
・シベリア
・中国
・東アジア
〇開花期
6月~10月です。
〇花色
黄色です。
〇耐暑性
強いです。
〇耐寒性
強いです。
〇特徴
開花期間が長いです。
オミナエシは花が咲く時期に個体差が大きく影響をしていまして、
早いものは6月から咲きます。
温かい地域では10月まで季節を跨ぎまして次々と開花をします。
花が終わりました後も色を残しますので、半年近くの間楽しむことが出来ます。
〇奈良時代から人気の花
オミナエシは日本最古の和歌集であります「万葉集」、
そして最古の長編小説であります「源氏物語」にも
その名が出てきます程歴史のあります花です。
綺麗な女性の例えや十二単(じゅうにひとえ)の色や、
庭に植えられました花として登場をします。
〇和歌
石川老夫(いしかわのおきな)さん
「をみなへし 秋萩折れれ 玉桙(たまほこ)の
道行きづつと 乞はお子がため」
このような歌をお詠みなられました。
@石川老夫さん
残念ながら詳細は不明です。
<意味>
「オミナエシと萩の花を摘みなさい。
旅の土産にと、子供が欲しがるから」
大伴宿祢池主(おおとものすくねいけぬし)さん
「をみなへし 咲きたる野辺を行き廻り
君を思ひ出 たもとほり来ぬ」
@大伴池主(おおとものいけぬし)さん
生没年 不詳 没年は推測ですが757年(天平宝字1年)。
系譜等 祖父麻呂さんの庶子とみる説、牛養の子とする説があります。
略伝 738年頃に珠玉を求むる使いとしまして、
駿河国を通過します。
春宮坊少属七位下
742年10月頃に平城京の橘奈良麻呂さん宅の宴に
出席をして歌を詠みます。
@橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)さん
721-757年
奈良時代の公卿(くぎょう)養老5年生まれ
橘諸兄(たちばなのもろえ)さんの長男です。
お母様は藤原の多比能(ふじわらのたひの)さんです。
政治的なトップの子息として生まれました。
出世は比較的に早く、20歳頃の740年に
初めて位階(いかい)を受けられました後は、とんとん拍子で出世を重ねます。
約10年程で「参議」に任命をされまして政治の中枢へと
仲間入りを果たします。
★橘奈良麻呂の編
「変」はのちに発生しました「藤原仲麻呂」さんの「乱」とは異なりまして、
あくまでも未遂です。
聖武上皇が崩御をされまして、その遺言に従い道祖王が立太子されますが、
仲麻呂さんの意向ですぐに配されます。
757年4月大炊王(後の淳仁天皇)が代わりに立太子される等、
仲麻呂さんの専横ぶりに奈良麻呂さんは強い脅威を感じます。
後ろ盾でありました父親が亡くなりまして、
藤原仲麻呂が一層権勢を強める状況に追い詰められた奈良麻呂さんは、
仲麻呂さんを武力をもって排除しようと謀反を画策します。
<意味>
オミナエシの咲いている野原を歩いているうちにあなたを思い出したから、
回り道をして会いに来ました。
〇秦八千島(はたのやちしま)さん
「ひぐらしの 鳴きぬる時は をみなへし
咲きたる野辺を 行きつつ見べし
@秦忌寸八千嶋(はだのいみきやちしま)さん
生没年、末詳、系譜等は不詳です。
秦氏につきましては、「秦」を宇氏とします氏族です。
東漢氏等と並び有力な帰化氏族です。
略伝 746年8月7日に越中国守として赴任して間もない
大伴家持(おおとものやかもち)さんの館で宴が催されまして、
大伴池主さん、土師道良さんらと共にこれに参席しまして
歌を詠まれましたようです。
@大伴家持さん
奈良時代の公卿で歌人です。
官位:従三位中納言です。
718-785年10月5日
大納言大伴旅人(おおとものたびと)さんの子供です。
三十六歌仙の一人で、小倉百人一首では中納言家持です。
「万葉集」の編纂に関わります歌人として取り上げられますことが多いです。
大伴氏は大和朝廷以来の武門の家でありまして、
祖父安麻呂(やすまろ)さん、父旅人さんと同じく
律令制下の高級官吏(かんり)として歴史に名を残しまして、
延暦(えんれき)年間には中納言にまで昇りました。
<意味>
「ひぐらしが鳴いている時には、オミナエシの咲く
野原をを散歩するのが最高です」
〇秋の七草
・オミナエシ ・ススキ
・カワラナデシコ ・キキョウ
・フジバカマ ・クズ
・ハギ
オミナエシは、炎症を抑えたり、膿を排出したりする働きがあるとされています。
〇名前の由来
「おみな圧し」「おみな減し」が転じたという説が一般的です。
@おみな・おんな
これらは特に美しい女性を表しています。
@圧し・減し
その美人を圧倒している。
女性の美しさが負けてしまう程の美しい花という意味があります。
やがて読みが「へし」から「えし」に変わりました。
〇花言葉
・約束を守る
・美人
・はかない恋
・親切
問題 オミナエシは様々な理由で自生地が少ないです。
その中でこちらの大蔵高丸(おおくらたかまる)という所には、
自生をしています。
大蔵高丸のあります都道府県を教えてください。
1、東京都
2、山梨県
3、群馬県
〇大蔵高丸 OO百名山 関東百山
標高:1781m
OO県大月市とOO市の境にあります山です。
@小金沢連嶺(こがねざわれんれい)
大菩薩嶺から南側へ続きます尾根筋を小金沢山(こがねざわやま)、
小金沢連嶺と呼びまして、その主峰となります小金沢山から、
牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま)、黒岳、
白谷ノ丸、湯ノ沢峠と経て当山に至ります。
@山名
OO市側にあります大蔵沢の上流にある高い山という意味がありまして、
丸は朝鮮語の峰を指す言葉といわれています。
@甲斐国志
甲斐の国の国の東の鎮(しず)めを「初鹿野山」としていますが、
この初鹿野山とは当山から南の大谷ヶ丸にかけての一体と
いわれています。
@山頂
南側のハマイバ(破魔射場)と共に富士山の眺望に優れます
秀麗富岳十二景の一つに選ばれています。
@花が美しい
登山口の湯ノ沢峠から当山の山頂から、
南側のハマイバにかけまして花の美しいコースとして知られています。
ヒント・・・○川尻金山
本栖湖から竜ヶ岳に向かう山の中にあります。
武田家の財政を支えました「OO金山」の一つで、
昭和初期まで採掘が続いていました。
採掘跡や金の鉱脈を辿(たど)って掘られた坑道があります。
お分かりの方は数字もしくは大蔵高丸のあります都道府県を
よろしくお願いします。


















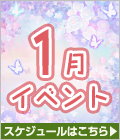
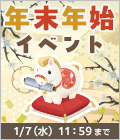











おお~、分かりましたか、正解です。
おめでとうございます(祝)
そうですか、それは楽しみですね。
はい、今夜は恐らくノエママンのおられます地域も蒸し暑いですので、
体調を崩されないようにご注意してお過ごしくださいませ。
どうもありがとうございました。
日曜、オツカレちゃ~ん☆彡(_´Д`)ノ~~オツカレー♪
2、山梨県☆彡(^_^)v
いつか、オフ会で、ワタピの美声をご披露するわネ♪(^_-)-☆
なんつって~☆彡ぶひゃ♪(≧∇≦)
無理せず無茶せず、体を労わりつつ、週明け月曜からもガンバルンバ~☆彡(`・ω・´)b