地名
- カテゴリ:日記
- 2011/05/27 06:39:39
地名を見ると、その土地に秘められた歴史が見えてくることがある。
たとえば、
三条町
=条里制(奈良から平安時代に組まれた区画制度)の跡。
そこだけ不自然に碁盤の目になっていることが多い。
江戸期の古地図と現在の地図を合わせると意外と一致する。
塩屋
=古代の製塩地。そのあたりまで海岸であったことを示す。
製塩土器(塩を作るために使用する)がそのような場所から出土されることもある。
東浜
=江戸時代の塩田があったことを示す。
江戸期の古地図を見ると、○○塩田と書かれていることがある。
松原
=東海道・西国街道などあるが、江戸時代の街道があった場所。
街道沿いに松を植えていたことが由来。
今でも松が植わっている。
馬屋
=南海道で馬屋を設けられた場所。
馬の墓が残っているところもある。
馬屋以外の地名で残っている場所もある。
泊
=潮待(潮流が速い地点で、そこだけだけゆっくりしている)地を示す。
平清盛厳島巡礼航路(そのような名前だったような)でも、
泊のつくところで、潮が変わるのを待っていたようである。
他にもかなりあるが今回はこれぐらいに抑えておく。
ただ総体的に上記の云われがある(古文書などの文献から)だけなので、
全てがそのような云われではないという事を付記しておく。
たまに古地図を広げながら、
現在の地図と見比べるのも面白いかもしれない。


















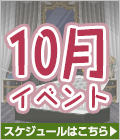








地方によって、方言で「○」が付くのはこういう地名、みたいなのも多くありますね。