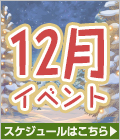前漢(西漢)・儒教国家へ
- カテゴリ:日記
- 2011/01/15 11:30:55
B.C.49年、宣帝が崩御、劉奭(元帝)が即位。
儒教に傾倒していた元帝は太子時代、宣帝に儒教重視の政策を提言したが受け入れられなかった。
そのため即位後は貢禹などの儒家官僚を登用し儒教的政策を推進していく。
貢禹の建議により宮廷費用の削減・民間への減税、専売制の廃止(すぐに復活)などの政策が実施。
貨幣の廃止による現物経済への回帰という政策も立案されたが実現しなかった。
貢禹の後を受けた韋玄成らにより、郊祀制の改革・郡国廟の廃止が決定され、七廟の制が話し合われる。
元帝の時代は儒教が政策の主導権を掌握し、儒教的イデオロギーが政治を決定するようになった時代である。
一方でこの時代には宦官および外戚の台頭も見られた。
宣帝の信任を受けた宦官の弘恭、石顕は、病弱な元帝に代わって朝政に介入するようになり権力を増大、遂には中書令に就任し政権を掌握した。
対して前将軍の蕭望之らは宦官の壟断を弾劾する文書を提出したが、宦官勢力により逆に罪に落とされ自殺に追い込まれた。
専横を振るった石顕も成帝の即位と共に失脚している。
漢と対等外交を志向して臣従を拒む西匈奴の 支単于に対しては、従前より臣従する東匈奴および西方で西匈奴と対立する烏孫と攻守同盟を結んで次第に追い詰めていった。
支単于は烏孫と対立する康居と同盟して部衆とともに北に移動したが、折からの寒気によって勢力を弱体化させた。
好機をとらえてB.C.36年、西域都護の甘延寿と西域副校尉の陳湯が独断で 支単于を攻め、 支単于を討ち取って西匈奴を滅ぼした。