■近代文藝之研究|研究|囚はれたる文藝(44)
- カテゴリ:その他
- 2010/06/11 03:45:56
■近代文藝之研究|研究|囚はれたる文藝 第九(5)
さはあれど、是等のもの多くは一に會して感情の本に歸るといへども、或るものは外れて再び舊の知識に行かんとするを免れず。已に自然といふ語生る、之を推し廣むる時は、所謂自然主義となるも已みがたき状勢ならずや。已に理想といひ、宗教といふ語用ひらる、其結論が哲理となり、教義となるもまた是非なき趣向にあらずや。而して、自然主義は、夫の寫實といふ近世の一潮流を併呑して、ます/\惡路に入り、遂に科學主義にまで墮せんとせり。佛のゾラ等は之れが代表者なり。哲理主義は、道徳問題、哲學問題、人生問題となりて、一派の作風を成せり。諾威のイブセン等是れに據る。また教義は遂にトルストイを宗教化したり。
我れ語れば多辯にして、談は十八世紀より十九世紀の後半にまで飛躍したり。言ふべき事盡きずして、夜はいたづらに更けんとす。中間は省除して、直ちに現代の二三子を場に登らすべし。」
--------------------
*註1:感情
「情」の正字体。「月」は「円」。
*註2:知識
「識」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/shiki.jpg
*註3:免れず
「免」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/men_manukareru.jpg
*註4:所謂
「所」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/tokoro.jpg
*註5:状勢
「状」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/jyou.jpg
*註6:宗教・教義
「教」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/kyou_oshieru.jpg
*註7:近世
「近」の旧字体。「シンニョウ」は「二点シンニョウ」。
*註8:併呑
「併」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/shikashi.jpg
*註9:ます/\
「/\」は踊り字・くの字点。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/odoriji.jpg
*註10:遂に
「遂」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/sui.jpg
*註11:代表者
「者」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/mono.jpg
*註12:道徳
「道」の旧字体。「シンニョウ」は「二点シンニョウ」。
「徳」の旧字体。「心」の上に「一」が入る。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/toku.jpg
*註13:諾威
ノルウェーの漢字表記。
*註14:世紀
「紀」の俗字(か?)。「糸」+「已」。
*註15:後半
「半」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/han.jpg
*註16:飛躍
「躍」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/yaku_odoru.jpg
*註17:更けん
「更」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/sara.jpg
--------------------
■抱月『近代文藝之研究』を註記なしに通しで読みたいかたは、こちらをどうぞ。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/kbk_tobira.html
■このテキストの原本は国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」収録の「近代文芸之研究 / 島村抱月(滝太郎)著 早稲田大学出版部, 明42.6」の画像データに依っています。
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/871630/1


















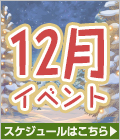










じゃなくて・・その・方が・たのしい・かな?
ただ・たんに・・ボーイ・ズ・ラ
ブ・嫌いじゃないよ・・マンガ・アニメ・わ・本物わ・ないない・安心して・・ラブコメ命だから
やっと・紫苑さんに・くんづけ・してもらったーーーーわーーーい
また・話きいてよーーーーぷぷぷぷー「ぷにしたの・今度わ
おれ・てきに・・・ども・・コメンターから・しもべ・になった俺「さゆ+紫苑
あ・・・スペードくん・専用でした「ふふふ」わ
こんにちは。読んでいただきまして、ありがとうございました。
この『近代文藝之研究』という本の初版は、1909年(明治42年)です。
この本の中でも、最も当時の文学界に影響力を持ち、また後世評価もされている論文が
deruvis さんが読まれました「囚はれたる文藝」で、これは1906年に書かれています。
日本が日清(1894年~95年)・日露(1904年~05年)の両戦争で勝利し、
欧米列強に必死に追いつこうとしていた……という時代背景があります。
島村抱月は1902年〜05年秋まで、イギリスとドイツに留学し、日本を離れていました。
「囚はれたる文藝」はその留学の間に吸収したり、考えたりしたことの、
主に文学に関するものの総括、といってよいと思います。
(島崎藤村の『破戒』を支持し、援護射撃する意味合いもあったようです)
文学史的には、日本の自然主義文学の理論的支柱として、島村抱月は記憶されていますが、
『近代文藝之研究』冒頭の「序に代へて人生觀上の自然主義を論ず」にあるように、
抱月自身はわずか3年で、すでに自然主義文学活動の行き詰まりを正直に吐露しています。
夏目漱石は抱月より4歳年上ですが、イギリスへの留学はちょうど1900年からで、帰国は1903年早々です。
滞在時期が少しオーバーラップしていますが、2人がイギリスで会ったということはなかったようです。
抱月が「囚はれたる文藝」を書いた年に、漱石は『坊ちゃん』や『草枕』を発表しています。
漱石の文章と比較すると、抱月の文章はずいぶんと堅苦しく感じられます。
抱月はちょうどこの「囚はれたる文藝」発表の頃から、演劇活動に軸足を移しはじめるのですが、
もともと抱月は、上京のおりには「美学・哲学を極めん」という志をいだいた学徒でしたし、
卒業後、坪内逍遥のすすめに従い、東京専門学校(=早稲田大学)に残った時も、美学が研究対象でした。
なので、抱月自身は、文学は美学の一分野としての研究対象として考えていただけのように思います。
つまり、「囚はれたる文藝」は文芸評論ではあるけれど、
本人は美学論文(哲学)の1つとして、研究者・学生向けに書いているため、
最初から新聞読者である大衆を対象とした漱石の文章とは、スタンスがちがっているのだろうと思います。
すごいです、何がすごいかって。
この文章が自分には異国の言葉に見えてきた。
現代文の成績は毎度悲惨なものなんでw
日本語は難しいです。